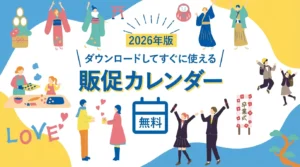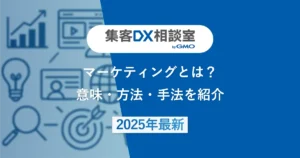2026年の販促カレンダー【無料プレゼント】

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。


2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。
顧客との信頼関係があれば長く付き合ってもらえる可能性は高いですが、自社の利益だけを優先しても顧客の気持ちを動かすことはできません。
この記事では、信頼関係を築くためのポイントを解説していくので、参考にしてください。
≪この記事は下記のような方におすすめです≫
急ぎの方はここだけチェック!
顧客個々の過去の購入履歴や好みに基づいたカスタマイズされたコミュニケーションが重要です。
SNS、電子メール、チャットボットなどを通じて顧客と接点を増やします。引き続きSNSの活用が重要です。
顧客データの分析により、より効果的なコミュニケーション戦略を立てます。
顧客からのフィードバックを収集し、ビジネスの改善に利用します。
顧客関係管理ツールを活用して顧客データを管理し、マーケティングキャンペーンの効果を測定します。
顧客に有益な情報や教育的コンテンツを提供し、ブランド信頼と関係構築を図ります。
その他の重要なポイントには、対面コミュニケーションや個別ミーティング、ウェビナーの開催、電話や手紙によるコミュニケーション、チャットツールやSMSの使用、メルマガやLINEの利用、SNSでの交流、チャットボットの設置などがあります。これらを組み合わせることで、顧客との関係を強化し、ビジネス成長に寄与します。また、テクノロジーの進化に合わせた新しいツールやアプローチへの柔軟な対応が重要です。
顧客との関係性を構築できると、売り上げに大きく貢献してくれます。顧客は、初めて相対する企業のことは何も知りません。
同じような商品を購入する場合は、知らない企業よりも知っている企業から買うのが一般的です。そのため、顧客との関係構築は売ろうとする前から必要になってくるといえます。
集客の第一歩として、まずは自社のことを顧客に知ってもらうことが重要です。
ただし、集客ができたとしても、顧客がずっとついてきてくれるとは限りません。しかも、良いサービスや商品は他社に模倣される可能性が高いので、品質だけを追求し続けて顧客をつなぎ止めるのは難しくなっているのが現状です。
自社の商品やサービスを長く使い続けてもらうためには、品質だけにこだわるのではなく、顧客との信頼関係を築いていくことをおすすめします。顧客とのコミュニケーションを通して信頼関係を構築し、企業のファンになってもらうことが重要です。
【関連記事】
顧客との信頼関係が構築されると、リピーターや優良顧客が生まれる可能性があります。
しかし、関係構築のメリットはそれだけではありません。そこで、この段落では顧客と信頼関係が構築できた場合の具体的なメリットを3つ紹介します。
商品やサービスを効率的に売り上げに結び付けるためには、顧客のニーズに応えることが重要です。
いくら市場調査やアンケートを行ったところで、ある程度の信頼関係がないと本音を聞き出すことが難しい場合もあります。信頼関係が構築できている顧客であれば、詳しく話を聞けるので、本当のニーズや課題を把握することが可能です。結果的に新商品の開発やサービス内容の見直しに良い影響を与えてくれるでしょう。
また、コミュニケーションを気軽に取れるような間柄になっていれば、顧客側からニーズや課題の細部まで話してくれるようになるケースもあります。
すると、顧客がどういったことで悩んでいるかを詳細に聞き出せるうえ、相談から解決まで迅速に対応できるようになります。
信頼関係が醸成してくると、「この人が困っているなら助けになりたい」という気持ちになってもらえることもあります。
すると、こちらが困っているときに手を差し伸べてくれるかもしれません。顧客が企業の場合は、相手が取り扱っているサービスやノウハウを自社に活かせるきっかけになるでしょう。また、顧客が個人であってもその人の人脈を活かして、思いがけず大きな助けになってくれる可能性もあります。
ただし、信頼関係の構築過程において、「最初から見返りを求めない」ことが大切です。あくまでも助け合いは信頼の上に成り立っていると理解しておきましょう。
関係構築によって人と人との対応が深まっていくと、企業と顧客との垣根を越えて個人と個人のつながりに発展させられることがあります。
すると、勤務時間以外で会う機会も増えて、自然とプライベートな話題について話し合う機会も増えるでしょう。気の合う仲間となれば、週末などに一緒にお酒を飲みに行って、個人の課題について相談したり、お互いの事業に関するアドバイスを送ったりすることもできます。
ビジネスライクの会話ではなく、より親身になってアドバイスをもらえるのは大きなメリットです。ときには、自社にはなかった価値観から、新しい商品やサービスの開発に役立つ情報を得られることもあるでしょう。
このような関係構築ができれば、双方の成長を目的とした関係になる可能性もあります。
【よく読まれている記事】

取引先が企業であっても、実際に相対するのは個人です。つまり、どのような場合であっても顧客は人間であり、気持ちを持っています。
無理に信頼関係を結ぼうとすると、拒絶されて関係が終わってしまう可能性もあるでしょう。そこで、関係を構築する前に、意識しておきたいポイントを3点紹介します。
まず、意識しておきたいのは「顧客との関係構築は、お互いの理解から始まる」ということです。
自社の顧客がどのようなタイミングで何を求めているのかを、まずは知ることが大切だといえます。相手のニーズを把握したうえで、自社の魅力や強みをアピールして顧客となってもらう方法が有効です。
そのためには、興味を持ってもらった段階で、「自社がどのような理念でどのような商品を作っているか」を顧客に知ってもらいましょう。
一般的に顧客側から必要もないのに、進んで関係構築を望んでくることはありません。ニーズに合致していると判断したら、企業側からさりげなくアプローチを進めていくことが大切になります。
顧客との関係構築を進めることで自社にとってはメリットがありますが、相手先にとっては必ずしもそうだとは限りません。
関係構築を進めるために一方的なアプローチを行うような、独りよがりな態度を取ってしまうと逆効果になる可能性があります。顧客側からすると嫌悪感だけが残って、信頼関係の構築が難しくなるかもしれないので、気を付けましょう。
ただし、顧客の要望に応えようとしてひたすら従順に従うのも問題だといえます。都合の良い企業だと思われてしまうと、対等な信頼関係が築きにくくなるからです。
自社と顧客との関係の理想形は「Win-Win」だといえるので、相手の御用聞きのような存在になるのは、やめておいたほうが賢明だといえます。
社会的な企業価値を落とさないためにも、応えられない要望に対してはきちんと理由をつけて丁寧に説明して断ることも場合によっては大切です。
顧客との付き合いが始まったからといって安心していてはいけません。
当然のことながら、自社のサービスや商品を購入してくれるのは、相手にとってメリットがあるからです。つまり、他に良いサービスや商品があれば、顧客はそちらに移ってしまう可能性もあるといえます。
また、企業としてもビジネスである以上は、信頼関係は「昔から付き合っているから」というような惰性のものではなく、利益を生み出すものでなくてはいけません。
ちょっとした魅力の違いで揺らいでしまうような関係性ではなく、中長期的な視点で密接なつながりを持った関係を構築することが重要です。
信頼関係が利益につながることを意識できれば、相手側も安心して顧客であり続けてくれるでしょう。
【関連記事】
\ 新規集客よりも効率的なリピーター集客/
顧客の心をつかむためには、相手に不信感や嫌悪感を抱かれるような行為は慎まなくてはいけません。顧客とのかかわりにおいて、避けるべき行為を4点ほど紹介します。
ネットワーク環境が発達した現代では、パソコンやスマホによる業務が多くなっています。
なかには、リモートワークのように顧客と一度も直接会うことなく、メールやSNSだけで業務が完結してしまう場合もあるでしょう。
しかし、メールやSNSは便利な反面、相手の反応や感情をつかむのが難しい点はデメリットです。やりとりをしている最中に相手の考え方や顔が浮かんでこないので、対応を間違えると顧客に不信感を抱かせてしまうケースがあります。
それに対して、直接会えば相手の反応や表情、言葉のテンポが分かりやすく、対応を間違えにくいでしょう。
また、最近ではWeb会議システムなど直接対面でなくとも相手の状況を把握しやすくなるツールも登場しているので、活用するのも一つの手でしょう。
意外に思う人もいるでしょうが、初めて見込み顧客のもとへ伺うときは、長居してはいけません。なぜかというと、相手も仕事中なので「興味のない話を長々と続けられるとかえって迷惑になる可能性があるから」です。
あまり長居すると、信頼関係を構築するどころか嫌悪感をもたれる可能性すらあるので、気を付けましょう。基本的に最初の数回程度の訪問は、挨拶とともに商品のパンフレットを置いていくだけで十分です。
滞在時間の目安は2分程度で、まずは担当者の顔と名前、自社の商品を覚えてもらうことだけを意識しましょう。
繰り返し接触を続けることで、2分程度の訪問でも相手の態度は徐々に軟化してくるはずです。場合によっては商品にも興味を持ってくれるので、そこから少しずつ関係構築を進めていきましょう。
相手と接触するときに意識しておきたいのが、相手先の役職です。
なぜなら、代表や事業責任者、担当者などの立場によって相手の思考や求めている解決策は異なるケースが多いからです。
たとえば、代表や事業責任者の場合であれば、課題解決の細かな手順よりも「できるかできないか」の明確な回答を求めるかもしれません。
反対に、担当者レベルの人と打ち合わせするときは、実際に問題を解決するための具体的な手順や、上司へ上申するためのエビデンス(根拠)を欲している可能性があります。
相手の立場や考え方に合わない提案をしても、商談がスムーズに進むことは難しいです。相手の立場を理解して、考え方に沿った解決策を提示することが大切だといえます。
業務で日ごろから複数の取引先を相手にしていると、忙しさのあまりつい機械的な対応をとってしまうことがあります。
特にメールや電話といった間接的な手段で対応していると、「人同士」で対話をしていることを忘れがちになるケースも多いです。すると、こちらにはその気がないにもかかわらず、知らないうちに相手に不快な思いをさせているかもしれません。
相手に興味を持ってもらうためには、「人間味のある対応」を取ることが重要です。そのためには、自分の個性を活かして対話するとよいでしょう。
自分の魅力が伝われば、相手への気遣いやもっと相手のことを知りたいという気持ちが高められるはずです。
顧客との信頼関係をどのように築いていけばよいか分からないという人のために、この段落では、実際に顧客の気持ちを動かして、信頼関係を構築するための行動を5つ紹介します。
相手の課題を解決してあげることを重点的に心がけていれば、紹介する行動はどれも自ずと出てくることでしょう。
相手が企業の場合は持っているニーズや課題だけではなく、企業の理念や価値観にまで興味を持ってみることが大切です。
会話のなかで可能であれば、関連する質問を投げかけてみるとよいでしょう。理念や価値観について尋ねることができれば、相手の会社に興味があることを明確に示せるはずです。
すると、相手も自社のこだわりに対して、熱意をもって話を聞いてくれる可能性があります。相手の理念や価値観について理解を深める過程で、課題の本質を発見できるケースも珍しくありません。
その点に沿って課題解決を提案できれば、企業の本質を理解してくれているという気持ちにつながって、強固な信頼関係を結べるでしょう。
相手の気持ちを変えるための方法とは、きれいな言葉遣いや過度なへりくだりではありません。
大切なことは相手の課題を一緒に解決してあげて信頼関係を構築することです。課題解決のためには数値や背景など、提案の根拠となる事実から目をそらすことなく会話することが必要になります。
ただし、提案する際は、知ったかぶりをしてはいけません。知らないことをそのままにしておくと、課題に対する適切なヒアリングができずより良い解決策を提示できなくなる恐れがあります。
知らないことは素直に質問をして、「知りたい」という気持ちを出したほうが、相手の信頼を得やすくなるはずです。
課題を解決するためには、必要に応じて相手先の現場スタッフと話をさせてもらうことも重要です。
なぜなら、スタッフ目線から会社の特性や課題の本質をつかむきっかけとなるケースも多いからです。特に相手先のトップと現場との間に距離感がある場合は、課題の本質についての意見に相違がみられるケースもあります。
担当者として仲介を行うことで、課題の本質について正しく理解し、解決へ導くことができれば相手の組織全体から大きな信頼を得られるでしょう。
ただし、現場視点を意識するといっても、仕事現場だけを訪れればよいとは限りません。ときには、朝礼や社内イベントといった風景にも顔を出してみるとよいです。普段とは違う会社の様子から課題解決の方法を発見できることもあります。
顧客との関係を密にするために、こまめな報告は重要です。なかには、相手へ気を遣って顧客への連絡をためらう人もいるでしょうが、基本的に報告はいくら行ってもやり過ぎということはありません。
むしろ、報告がない期間中は、こちらがどれだけ業務を進めていたとしても、進捗状況について顧客が知るすべはないことを意識したほうがよいです。
つまり、報告までの期間が長くなるほど、顧客は不安を抱えることになります。
何かアクションを起こしたときや、進展がみられたときはメールでもいいので、経過を報告することが大切です。
自分のために動いてくれているという印象を絶えず与えることで、信頼を引き寄せられるでしょう。
また、こまめな連絡の実施は、内容や方針に対する認識のずれがあった場合でもすぐに修正できるメリットもある点は覚えておくとよいです。
信頼関係を強くするためには、「相手が喜ぶことは何かを意識しながら動くこと」が何よりも大切です。
たとえば、稟議書や参考資料の作成といった事務的な負担への支援や相手先のプロジェクトにおける課題への提案などが挙げられます。頼まれていないにもかかわらず、相手の悩みを先読みして動くことは、相手の想定を上回る結果を出すことです。その積み重ねによって「あの人なら任せられる」という信頼が生まれてきます。
もちろん、相手のためにする行動はすぐに自社の利益に結びつくわけではありません。どちらかというと、先行投資のような意味合いがあるので、短期的なビジネスライクを重視するうえでは問題がある可能性もあります。
しかし、利益だけを重視した関係では、仕事の状況が変わると、すぐに崩れてしまうことでしょう。強固な信頼関係を築くためには、ビジネスライクだけではなく、相手に寄り添った対応が必要なのです。
インターネットが普及したことにより、顧客とのコミュニケーション手段が従来よりも格段に増えました。「時間や場所の制約があるもの」「顧客の反応がすぐに見えるもの」など、ツールや手法によって特徴がまったく異なります。
顧客にとって最適な方法を選ぶことが重要です。
この章では、オフライン・オンラインを問わずに選んだ11個のツール・手法を顧客との距離が近い順に紹介します。
顧客と直接会って話をすることは、信頼関係を築くうえで非常に重要です。
非対面のコミュニケーションよりも表情や行動から感情を読み取りやすくなり、ニーズを汲み取る手助けとなります。
言葉で説明しづらい内容を伝えたい場合は、オンライン上で顧客との個別ミーティングをすることが効果的です。
たとえば、家電修理や中古車査定など、担当者を派遣しなければならないケースでも、ビデオ通話を利用すれば状況を把握できます。
ほかにも、部屋の賃貸契約前にテレビ電話を利用して内覧を済ませることも可能です。
映像をつなげることで、より精度の高いサポートを提供できます。
オンラインセミナー(ウェビナー)を開催することで、場所を問わずに複数の顧客とコミュニケーションを取ることが可能です。
ただし、展示会や説明会とは異なり、すぐに商談に入ることが難しいため、ウェビナーを開催した後におけるフォローの仕組みを用意しておく必要があります。
メールやSMSなど、オンライン上でのやりとりが主流になった現代でも、電話の重要性は変わりません。
とくにPCやモバイル端末を利用しない顧客とは、電話でのやりとりがもっともリアルタイムで確実にコミュニケーションをとるツールとなります。
また、電話は他のツールに比べ、感情がダイレクトに伝わりやすい特長があります。
電話での応対で高い評価を受けることができれば、顧客からの信頼を得られやすいでしょう。
コミュニケーションの手段として、顧客に手紙を送ることも有効です。
オンラインでの交流よりも手間と時間がかかる手紙をあえて利用することで、顧客は特別感を感じやすくなります。
顧客に思いを伝えるためのツールとして手紙を利用することもひとつの手段です。
顧客とのやりとりが頻繁に発生する企業では、チャットツールが有効です。
電話やメールよりも素早く、より手軽に連絡を取れます。
そのため、問い合わせのツールとして、チャットを活用している企業も多くみられます。
ただし、レスポンスが遅ければ顧客に不信感を抱かせる原因になるでしょう。
そのため、知識が豊富で対応の早い人物を担当者に据えることをおすすめします。
顧客情報に携帯番号が含まれていれば、SMS(ショートメッセージサービス)を利用してメッセージを送れます。
SMSは、本人認証やパスワード認証に利用されていることから、個人情報としての信頼性が高いといえるでしょう。
また、メールに比べて開封率が比較的高く、確実に伝えたいことがある場合に有効な手段といえます。
メルマガは顧客個人とのコミュニケーション手段というより、広告としての側面が強いツールです。
定期的に送信することで顧客との接点を維持できます。
また、顧客情報をカテゴリーに分類してリストにすることで、ターゲットに合ったコンテンツを提供しやすいことも特徴です。
個人にとって有益な情報を送信することが、開封して読んでもらうためには重要です。
LINEでは企業で利用する公式アカウントと、個人アカウントという2種類のサービスを提供しています。公式アカウントでは以下のサービスが利用可能です。
接客業においては、より個人的に顧客とLINEを交換することも、親密度を高めるうえで有効的な手段です。
SNSは国内での普及率が8割ともいわれています。
社会に対して強い影響力を持ち、マーケティングには欠かせないツールを確立しています。
既存の広告とは異なり、顧客と直接交流できることが特長です。
SNSの影響で商品を購入するケースも多く、適切に活用できれば売上の大幅な増大が期待できるでしょう。
顧客の問い合わせに対して即座に対応できることが、チャットボットを設置する最大のメリットです。
よく使われている方法として、FAQページとの組み合わせがあります。
顧客の質問に対する回答が記載されたページをチャットボットが提示し、該当のページがなければオペレーターが対応するという流れが一般的です。
顧客とのコミュニケーションを構築するための戦略には、以下のようなものがあります。
詳しく調べて、自社のコミュニケーション戦略に役立てましょう。
自社製品につながる、顧客にとって価値のある情報を配信することで見込み顧客を獲得し、販売につなげる戦略
ファネルとは顧客の行動を認知・検討・購入の3段階に分けたものを指し、フルファネルとはそれら3つの段階全てにアプローチする戦略を指す
自社製品の情報や試供品などを提供することで、新規顧客にアプローチする戦略
既存顧客に対して付加価値を提供することで、さらなる信頼関係を構築する戦略
マーケティングで使用される「アクイジション」とは、新規顧客の獲得や開拓を意味します。
ここでは、マーケティングにおける「アクイジション」の概要や方法、施策実施の上でのポイントを解説します。
アクイジション(英語でAcquisition=「取得」「獲得」)とは、新規顧客を獲得するマーケティング手法です。「M&A」という、企業の合併や買収を意味する言葉があります。この「A」が、アクイジションです。
アクイジション(Acquisition)
https://ja.wikipedia.org/wiki/アクイジション_(曖昧さ回避)
マーケティング用語。販売促進活動において、見込み顧客を顧客に変化させるための過程を言う。例えば、商品・サービスに関する詳細な情報を提示する、試用品を提供する、などの手段が取られる。
新規顧客から売上を獲得するには、まず顧客を見つけ、さらに見込み客に対して自社のサービスや商品を知ってもらう必要があります。そのため、既存顧客に比べて時間と手間が約5倍もかかります(「1:5の法則」)
具体的には、自社の試供品や、サービスや商品の詳細な情報を提供することなどが挙げられます。
アクイジションは新規顧客の獲得を意味します。それに対し、リテンションは既存顧客との関係の維持を意味します。
見込み客を見つけることから始めなければならないアクイジションに対し、リテンションは、既存顧客との関係維持に関する活動です。
そのため、売上を獲得するためにかかる時間や手間は、そこまで多くはありません。
リテンションの活動には、例えば解約や乗り換え防止に特典を用意する、リピート購入してもらう、などがあります。
前述の通りアクイジションは、「獲得」「取得」を意味します。つまり、新たな顧客の獲得です。
「取得」が受動的であることに対し、「獲得」は自発的で積極的な意味合いを持ちます。そのため、マーケティングにおいては「獲得」の意味で使用されることが一般的です。
サービスを成長させるための成長戦略モデルの一つに、「AARRR」と呼ばれるものがあります。アクイジションは最初の入り口となる「A」(新規顧客の獲得)を意味しています。
いくら商品やサービスがよいものでも、知られていなければ意味がありません。
企業として高い利益を出すためには、人に知られる必要があります。利益を増やすためにも、アクイジション施策は非常に重要です。
参考:AARRRとは〜サービスを成長させるための基本戦略【テンプレート付】|ferret
アクイジションの施策は、企業が相手の「BtoBビジネス」と、一般消費者が相手の「BtoCビジネス」とで異なります。
BtoBにおけるアクイジションは、営業担当者が見込み顧客の情報を集めるところから始まります。例えば、営業担当者による訪問や、相手企業との面談のためにテレアポをする、などです。
そして、BtoCにおけるアクイジションは、消費者に商品やサービスの宣伝や広告を打ち、マーケティングによって進めます。例えば、SNSで広告を打つ、チラシをポスティングする、などです。
アクイジション施策を実施する上でのポイントは、主に下記の3つがあります。
それぞれについて、解説します。
アクイジション施策を行う際は、短期と長期、両方の施策を同時に展開しましょう。
なぜならアクイジション施策には、短期で効果の出る施策と、効果が出るまで時間のかかる施策があるためです。
例えば、SNS広告やテレアポなどは、試作開始と同時、もしくは短期間で効果が実感できます。
一方でサイト内のコンテンツ配信やSEO対策、SNSのアカウント運用などは、施策を開始しても、すぐには結果が出ません。効果を実感できるようになるまで、施策を長期的に続ける必要があります。ただ、効果が出始めたら安定した効果を得られます。
そのため、短期と長期両方の、バランスのよい展開が重要です。
競合他社の行うアクイジション施策を分析しましょう。
なぜなら、競合が行っているのであれば、成功している施策である可能性があるためです。特に、長期間継続している施策は分析する優先順位を高くすべきです。
また、実施後の結果を分析し、その後の施策に反映していきます。
ユーザーのニーズについても、常に意識しておきましょう。
なぜならユーザーからは、自分の抱えている問題を解決できる手段が、求められているためです。ユーザーの問題とは別の視点から訴求していても、結果にはつながりません。
自社が売りたいものだけではなく、ユーザーの知りたい情報や願望を叶えるサービスや商品を提供すれば、必ず売上向上につながります。
顧客と信頼関係を結ぶには顧客の課題を発見し、解決することが重要です。そのためには、相手の気持ちに寄り添う対応がまずは必要だといえます。
紹介した内容を参考にして顧客との関係構築を進めていきましょう。
デジラボでは、関係構築の対象となる顧客をどう集めるか、どうマーケティングしていくかといったお役立ち情報を発信しています。

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。