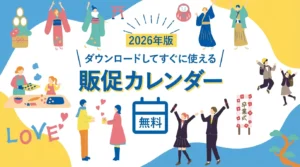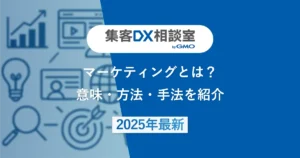2026年の販促カレンダー【無料プレゼント】

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。


2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。
企業が売り上げをアップさせるためには、ただ商品を売ったりサービスを提供したりするだけではダメなこともあります。消費者がどんなものを望んでいるか、どういう状況ならば商品を買ってくれるかなどがわかれば、効率的にビジネスを展開することが可能です。
そんなとき、消費者行動モデルを知っていれば役に立ちます。そこで、ここでは消費者行動モデルの変遷やビジネスへの役立て方について詳しく説明します。
≪この記事はこんな方にオススメです≫
消費者行動モデルは、消費者が広告などで商品を知ってから、実際に購入するまでの間のプロセスをモデル化したものです。
マス広告しかなかった時代、最初にモデル化されたのがAIDAでした。その後、インターネットが普及し、さらにSNSで情報が拡散されるようになるにつれて、消費者行動にも変化が出てきたのです。
そこで、次の章からは、消費者行動の変化とともに生まれてきた消費者行動モデルについて、順を追って紹介します。
消費者行動のモデル構築はすでに1900年代に入る前後から始まっていました。
アメリカ人のSt.エルモ・ルイスが1898年にAIDAのもととなる「AID」を提唱しています。AIDのAは「Attention(注意)」、Iは「Interest(興味、関心)」、Dは「Desire(欲求)」の頭文字です。その後、St.エルモ・ルイスは1900年になってから「Action(行動)」を最後に加えています。
ただ、このAIDAが有名になったのは、ルイスがAIDAを提唱してから25年経った1925年でした。ルイスと同じくアメリカ人のE・K・ストロングが、自身の論文のなかでAIDAモデルを使い、セールスに関して顧客の心理を説明したのです。
AIDAの法則では、まず消費者は広告を見ることで商品を知ります。これがAttention(注意)の段階です。
広告を見て興味を引かれ、欲しいと思います。つまり、Interest(興味、関心)とDesire(欲求)の段階に進みます。
そして、実際に商品を買おうと行動を起こすAction(行動)の段階に続くモデルです。
AIDAの前身であるAIDが提唱されてからすでに100年以上経っている現代でも、AIDAの基本概念は消費者行動のベースであると考えられています。
AIDMAもAIDAと同じアメリカで提唱された消費者行動モデルのひとつです。
販売や広告に関する著書を多く発表していたサミュエル・ローランド・ホールが、1924年に自身の著書『Retail Advertising and Selling(小売りにおける宣伝と販売)』のなかで発表しました。
AIDAはAttention、Interest、Desire、Actionの4段階だけでしたが、AIDMAではDesireとActionの間に「Memory(記憶)」が入ります。
5つの段階を踏むAIDMAの理論は、認知段階と感情段階、行動段階の大きく3段階に分けた考え方をすることが特徴です。広告を見て商品のことを知る認知段階にはAttentionが含まれ、行動段階にはActionが入っています。そして、感情段階に含まれるのがInterestとDesire、Memoryという3つの段階です。
広告で商品を見て興味を示し、さらに欲しいと思った感情を記憶にとどめておくという段階が加わったのです。
消費者は実際に広告を目にして欲しいと思っても、必ずしもすぐに行動を起こすとは限りません。たとえば、その時点では購入するための資金がないこともあるでしょう。
また、休みになるまで買いに行けないという事情があるかもしれません。さらに、単にちょっと欲しいと思っただけで、実際に購入しようかどうか少し迷いがあるということもあり得ます。
ただ、広告を見たことを記憶しておくことで、買い物に行ける機会が訪れれば購入するという行動につながることもあるのです。
AISASは日本の電通が2004年に発表した消費者行動モデルです。
インターネットが普及するまでは、新聞や雑誌など紙媒体の広告や、テレビやラジオのCMなどでしか商品の情報を知る手段がなかったと言えます。
新聞や雑誌、テレビやラジオによる広告の場合、ほとんどの消費者は提供される情報を受け取る立場でしかありませんでした。しかし、インターネットが普及し、いつでも誰でも自由に使えるようになったことで、消費者の行動にも変化が出てきたのです。
インターネットでは、消費者が自ら興味を持ったものを検索して情報を得ることができます。また、SNSを使って消費者自らも情報を発信できるようになりました。そんな状況の変化を受け、消費者行動モデルにもインターネットの普及以前にはなかったプロセスが加わっています。
AISASのAは、AIDAやAIDMAと同じAttention(注意)、その次のIもInterest(興味、関心)で同じです。しかし、その次にインターネット時代では、Search(検索)という段階が入ります。なにか興味を引くことに出会ったとき、インターネットを使って自分で調べてみるという行動を起こしたことがある人は多いでしょう。AISASでは実際に商品を購入する前に対象のものを検索し、その結果を考慮して購買するかどうかを決めるという行動が入ったのです。
そして、SearchしたあとにAttention(行動)の段階がありますが、インターネット時代は購入して終わりというわけでもありません。
誰でもSNSで自分のことを発信できるようになったため、いいものを買えたりいい体験ができたりすると、Share(共有)するという段階もあるのです。
AISASでも認知段階(Attention)と感情段階(Interest)、行動段階という3つの段階に分けられます。ただし、AIDMAでは行動段階がActionひとつだったことに比べると、AISASではSearchとAction、Shareという3つが含まれるのが特徴です。
2005年になると、アンヴィコミュニケーションズがAISASをさらに詳細にしたAISCEASを発表しています。AISCEASではAISASで示されたSearch(検索)のあと、実際に購入するというActionを起こす前に、「Comparison(比較)」と「Examination(検討)」が入りました。
つまり、インターネットを使ってSearchしたあと、他の選択肢を含めて比較し、購入するかどうかを検討するというプロセスも消費者行動を考えるうえで大切だと考えられるようになったのです。
実際、商品の購入を考えてインターネットで検索する場合、ひとつの情報だけで決めてしまう人は少ないと言えます。いくつかのWebサイトで複数の情報を集め、似たような商品と比較し、どれを購入しようか検討することがあるはずです。
もちろん、インターネットがなかったマス広告が主流の時代でも、消費者が複数の商品を比較・検討することはあったでしょう。ただ、誰でもインターネットを使って多くの情報を集められるようになったことで、消費者行動を考えるうえで比較や検討の段階もより重要なプロセスになりました。
ZMOTは「Zero Moment of Truth」の略で、Googleによって2011年に提唱された用語です。ZMOTはマス広告の時代に提唱されたAIDAやAIDMA、さらにインターネット時代に入ってから提唱されたAISASのような理論とは少し考え方が異なります。
ZMOTは消費者が商品を購入しようと店舗を訪れるよりも前、つまり、ゼロの段階ですでに購入する意思を固めているという考え方です。つまり、インターネットで事前に商品に関して詳細を調べて意思決定を済ませてしまうため、企業側はインターネットでの情報発信が重要になります。
2010年頃からのソーシャルメディアを利用する消費者が多くなった時代に、新たに提唱されたのがVISASです。
VISASは「Viral(口コミ)」と「 Influence(影響)」、「 Sympathy(共感)」、「 Action(行動)」、「 Share(共有)」の頭文字をとっています。
つまり、インターネットで検索して比較・検討するという消費者の行動がさらに変化し、利用した人の口コミなどに影響を受け、後押しされて購買という行動につながることが多くなっているのです。
さらに、2011年には「Sympathy(共感)」、「Identify(確認)」、「Participate(参加)」、「Share & Spread(共有・拡散)」の頭文字を冠したSIPSが提唱されました。
SIPSではSympathy(共感)から始まるところが特徴的です。
つまり、企業側からのアピールがなくても、知人や影響力を持つ人が発するメッセージに共感し、共感すればその情報について確認するという流れになっています。そして、いいと思えば「いいね!」するなど、自分でもソーシャルメディアを使って発信すれば、企業の広告にParticipate(参加)することになるのです。
結果として、共感の輪が広がっていくことになります。
さらに最近では株式会社ホットリンク執行役員 CMO 飯髙 悠太氏によって「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」、「Like(いいね!)」、「Search1(SNS検索)」、「Search2(Google/Yahoo!検索)」、「Action(購買)」、「Spread(拡散)」の頭文字をとったULSSASが提唱されました。
ULSSASの特徴はUGC(ユーザーが投稿したコンテンツ=ネット上の口コミなど)から始まり、Like(いいね!)をさせ渦巻きのように態度変容をさせながら、Spread(拡散)を経て、Like(いいね!)に戻るところにあります。
重要なことは、商品やサービスの質を高くすることでUGCを生み出してもらえるようにすることです。
2015年あたりからコンテンツマーケティングの時代に入り、「Discovery(発見)」、「Engage(関係)」、「Check(確認)」、「Action(購買)」「eXperience(体験と共有)」の頭文字を使ったDECAXというモデルが提唱されました。
情報があふれている現代では消費者が多くの情報を得ることができるようになり、自分で必要な情報を探すようになっています。
そんな状況の中で消費者の共感を得られる情報や求める情報を、消費者自身に見つけてもらうDiscovery(発見)からスタートしている理論です。
有益な情報を見つけたらその情報発信元との関係を深め、詳細を確認することで購買、さらに体験したことを共有するにつながります。
このモデルで重要なことは、商品を売り込むための情報発信ではなく、消費者にとって役立ち、信頼できる情報を発信することで関係を深めて購入につなげる、ということです。
DualAISASはインターネット時代に提唱されたAISASを、コンテンツマーケティング時代に合うように進化させたモデルです。
消費者の商品を買いたいという感情に、他の人にも広めたいという感情をプラスしています。
DualAISASのAISASの部分は、「Active(起動・活性化)」、「Interest(興味)」、「Share(共有・発信)」、「Accept(受容・共鳴)」、「Spread(拡散)」です。
商品を広告で見て知って欲しいと思ったとしても、最終的に商品を買うという行動につなげることができなければ広告を出す意義が半減します。
消費者行動モデルに当てはめて考え、どこかの段階でストップしているのなら、修正や対応が必要だということです。
たとえば、AIDAやAIDMAモデルの場合、Interest(興味、関心)の段階では、消費者の注意を引く広告ができているかどうか、また、消費者のニーズを満たすものであることがアピールできているかどうかを考える必要があります。
アピールポイントがわかりにくい広告ではなく、一目見て消費者がメリットを把握できることが大切です。また、期間限定などのキャンペーンを組み込めば、今買っておかなければという行動に移りやすくなるでしょう。
また、AIDMAでは5つの段階の中にMemory(記憶)が入っていました。AIDMAのモデルに基づいて考えると、一度広告を見て興味を持った商品を思い出してもらうことが大切になります。
一度顧客からのアプローチがあったのならば、電話やDMなどでフォローすることで商品を思い出してもらい、購入につながることもあるでしょう。
商品を思い出しやすいキャッチフレーズが浸透していたり、CMの映像が印象に残っていたりすると、いざ購入すべき時期がきたときにライバル商品の中から選ばれやすくなるのです。
たとえば、「引っ越しのサカイ」という愛称で知られるサカイ引越センターは、長年印象的なCMを多く制作しています。
古くは1989年から俳優の徳井優さんを起用して始まったCMが一例です。
「べんきょうしま~っせ引っ越しのサカイ、ほんま~かいな、そうかいな」などコミカルなフレーズが流れて頭に残りやすいCMでした。
また、2010年以降にはドラマ仕立てのCMに転換し、今度はCM中で引っ越しのサカイのトラックが走るスポットが注目されるようになったのです。
そのなかのひとつである滋賀県高島市にあるメタセコイア並木は、もともと地元ではそれなりに知られた場所であったものの、CMをきっかけに全国規模で知られるようになりました。
引っ越し自体は、それほど頻繁に行われるものではありません。しかし、実際に引っ越ししなければならない状況になったとき、CMが印象に残っていたことが理由で選ばれることもあります。
インターネットを利用するのが当たり前になった現代では、SEO対策をはじめ、検索したときにヒットしやすい情報発信をすることも大切です。
特にDECAX理論によれば、まずは消費者に自社のWebサイトをDiscovery(発見)してもらわなければ、ライバル社の情報の中に埋もれて商品やサービスを認知してもらう機会を失ってしまいます。
また、単に目を引くものを適当に発信すればいい、検索に引っかかりさえすればいいというだけではなく、正確で信用できる情報を載せたコンテンツでなければ消費者の信頼を得ることはできません。
さらに、SNSでの情報共有や口コミで共感が広がることを期待するのならば、SNSで拡散してもらえる環境も整える必要があるでしょう。
【関連記事】
アプリ市場のこれからの展望は?今後さらに伸びていく市場を解説!

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。