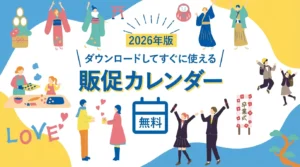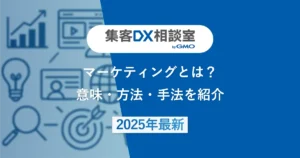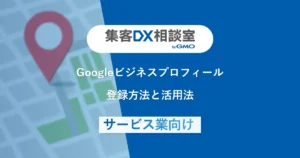2026年の販促カレンダー【無料プレゼント】

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。


2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。
業務効率化を自社でもしないといけない。そう思っている方でもやり方がわからなくてお悩みの方も多いはずです。
近年、日本の今までの働き方に問題があると捉えられるようになってきました。その結果、働き方改革が求められるようになってきています。
2020年は新型コロナウイルスの問題によりテレワークが多くの企業に導入されるなど、さらに働き方の変化は加速しています。
クリエイティブなアイデアによって業務効率をより向上させることで、得られるメリットというのは実は非常に多いのです。
今回はどのように業務効率化を推し進めていけばいいのかをご紹介していきたいと思います。
2019年に公益財団法人日本生産性本部により発表された労働生産性の国際比較データにおいて、日本の労働生産性はOECD加盟国36カ国中21位です。主要先進国(7カ国)と比較しても、1970年以降、最下位の状況が続いています。
よく海外では日本人は勤勉であるといわれますが、業務効率が悪いことを揶揄して「表面的には真面目」といわれることもあります。
実際、長時間労働が問題になるなど、日本における業務効率は決していいといえるものではありません。
そこで提唱されたのが「働き方改革」です。
これは、今までの労働形態に含まれていた「ムリ・ムダ・ムラ」を是正することで、業務の効率化を図ろうとする改革。企業の売上向上や、従業員の労働環境を改善させるために行われています。
つまり、働き方改革に伴う業務効率化は、経営を強化するというだけでなく、従業員個人の周囲環境を整備するなどの従業員の待遇の改善を含め、「会社全体の改善」を目的としているといえます。
業務効率化はよく生産性向上と混同されがちです。
しかし、実際にはこの2つは手段と目的の関係にあります。つまり、業務効率化を果たすことで、生産性の向上が期待できるということ。
このように、生産性向上は業務効率化のメリットの代表例ですが、他にも業務効率化にはまだまだメリットが存在します。
まず、経営に目を向けてみましょう。
業務効率化では、必要以上に予算を占めていた業務が削られることになります。つまり、不必要なコストを削減することができます。
このコストカットの影響は経理面での影響にとどまりません。
不必要な業務に割いていた人材・リソースを他の業務、あるいは従業員の賃金に回すことができるようになるので、成長分野への投資や、従業員のモチベーション向上などにつながります。
また、業務効率化によって、業務はある程度システム化されます。
システム化によるメリットは甚大です。業務のシステム化によって、作業効率は上昇するだけでなく、ある一定の業務に必要な人手が少なくなります。
そのため先ほどと同じように人材を適材適所に配置できるようになるでしょう。
業務がシステム化し、専門的なスキルを必要としなくなった場合、その業務の門戸が広がるというメリットもあります。
従業員個人に目を向けると、効率化は疲労の削減にもつながりますし、賃金の上昇も期待できるのです。
処理スピードがあがり残業などが少なくなることにより、ワークライフバランスを保つことができるようになるというメリットも見逃せません。
ここまでで、業務効率化の目的やメリットについてわかってもらえたかと思います。
それでは、業務効率を上げていくための具体的なアイデアや成功事例を見ていきましょう。
問題解決のヒントは現場にあるという言葉もよく聞きますが、業務効率化の本質は、不必要な部分である「ムリ・ムダ・ムラ」を削減してくことで、それは現場の声からわかります。
まずは何が必要で何が不必要なのかを判断する必要性があります。
会社の部署単位で削減していくケースから、会社の部署内での作業のムダを削減してくケースまであることからわかるように、ここでの削減の対象は大小さまざまです。
そのため、現場を知らない状態で各ケースごとに机上の空論を交わすよりも、現場での聞き取り調査によって実態を把握するべきです。
人間の集中できる時間というのは、個人差こそありますが、限界があります。
朝から晩まで、昼休憩のみで集中力が続く人はほんの一握りです。そのため、1時間ないしは2時間に1度程度休憩を入れると効果的だったという成功事例があります。
このように、根性論ではなく、科学的・合理的に人体をいたわってあげるというのは業務効率化において重要なポイントです。
現状の把握という意味で、聞き取り調査とともに効果的なのが、業務の「見える化」です。
ここでの業務の「見える化」とはどういう意味かというと、業務を客観的なデータで表すということです。
たとえば従業員の各業務にかかる時間を測定したとしましょう。その測定結果には、各従業員の得意・不得意あるいは、能力が現れています。
得意なところに従業員を専念させるようにすることで、品質・サービスの向上や時短を図ることができます。
現在行っている業務についての現状分析が終わってまず考えるべきは不必要な業務をなくすことです。
不必要な業務は単純に「ムダ」です。将来的に何かに役立つ可能性は否定はできませんが、合理的に考えると現在必要でないものはどんどん削減すべきでしょう。
部署がマルチタスクな業務を担っていると、どうしても業務の切り替えというものが存在します。
この時間が「ムダ」で、従業員に「ムリ」をさせるような業務構造は破棄すべきです。
部署の中でもさらに細かい最小単位の「チーム」を組み、各チームは業務プロセスの中でも一つのタスクのみを担うべきです。
そしてそのタスクについての決裁権を各チームに与え、決裁権を細分化することで、意思決定プロセスの伝達が早くなります。
今までは、まさに業務の削減や振り分けについて述べてきましたが、実は、業務以外の要素も業務効率にかかわってきます。
綺麗な環境はいい業務につながります。
機械以外では業務を行うのは結局人間なので、従業員の周囲の観光を整備することで、従業員のモチベーション向上につながり、作業効率の向上が期待できます。
環境の整備の際には3S(整理・整頓・清掃)に気を付けるとよいでしょう。
科学技術が進歩してきて便利なITツールが登場してきました。
特にデータの管理や、意思決定ツールに関しては導入する価値が大きいといえるでしょう。
たとえば、データ管理の面では、クラウドストレージサービスはほとんど必須といっていい存在になっています。
これはデータ管理という意味でもそうなのですが、社内であれば情報を共有することができるので、意思決定の迅速化にもつながるという意味でも重要です。
ITツールにはRPAというものも含まれます。
RPAとは、ロボティックプロセスオートメーションの略で、今までは人間が行っていた業務内容をロボットに行わせるということです。よく聞くAIなどもここに含まれます。
まだ完全に人間にとって代わることが難しい業務が多いですが、データ処理などに関しては、機械に任せた方が圧倒的に効率が良いので導入が進んでいます。
業務を行うにあたって、個人の判断に委ねる部分が多いと、どうしても判断ミスが起こってしまったり、業務に「ムラ」ができてしまいます。
そこで、あらかじめ行う業務内容を画一化することが業務効率化には必要であるとされています。
そのためにマニュアルやフローチャートなどを作成すると、業務の流れがわかりやすくなるのでおススメです。
データベースというのは、会社が今まで蓄えてきたデータのことです。
何をすれば、顧客のリピート率や客単価が上がったのかなどのマーケティングの部分では特に、過去のデータを収集し、分析することで何が効果的だったのかを洗い出すことができます。
過去のミスについてのデータも社内のデータベースには含まれているので、データベースを用いると、過去に起こしたミスを防ぐという意味でも業務効率を改善することができます。
日本の景気停滞・後退が危惧され始めて久しく経ちますが、この状況を打破するには各企業が今までの働き方を見直し、業務効率化を果たすための努力をすることが必要です。
業務効率化によって、会社の売り上げを向上するだけでなく、従業員もワークライフバランスを保つことができるようになります。
そのための方法がわからないという方は、ここで挙げた10の方法を試してみてください。

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。