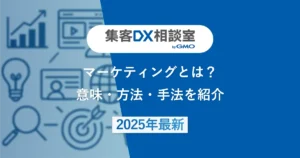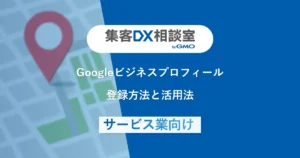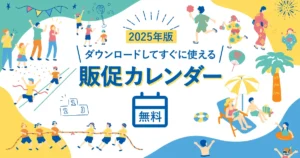2025年6月はじまり販促カレンダー【無料プレゼント】

2025年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。


2025年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。
顧客満足度向上の重要性や方法・成功事例について解説しています。
店舗や企業にとって顧客満足度(CS)の向上は非常に重要な位置づけのテーマであり、近年の店舗・企業の売上の向上においては絶対に不可欠な要素です。
ただ多くの方が顧客満足度の重要性を理解していても、具体的なCS向上施策に落とし込めていないケースも多いでしょう。
今回は以下のような方に向けて顧客満足度について紹介します。
顧客満足度は何か?というと商品やサービスに対して、顧客がどれだけ満足しているかを数値で表した指標です。
顧客満足度は英語で「Customer Satisfaction」と表記され、略して「CS」とも呼ばれています。店舗や企業が集客を目指す際には、提供側の目線ではなく何よりもお客様目線でマーケティングをしなければいけませんので、顧客満足度は顧客優先の為のマーケティングの成功を図る指標ともいえるでしょう。
顧客満足度向上(CS向上)とは、顧客満足度を高めること。つまりは顧客が自社の提供しているサービスを利用したり、商品を購入した際の評価を高めることを指します。
どのような感想を抱いているかを顧客目線で分析し改善していくことが必要で、顧客満足度改善により再度同じサービスを利用したり、別な商品の購入につながるケースもあります。
このように、顧客満足度向上にはビジネスにおいて売り上げ確保という側面でも大きなメリットがあるのです。
次の項目でさらに具体的に説明していきます。
なぜ顧客満足度の重要性が語られるようになったのかというと、品質や価格だけで顧客に訴求するのでは、売上につながりにくくなっているからです。
全てが間違いではもちろんありませんが、こんな風に品質や価格をただ顧客にアピールをしていても、ライバル商品との差異は伝わりにくいといえます。
また、単純な価格競争に持ち込もうとすると本末転倒で、店舗や企業の肝心な利益が広告などの費用により減少しかねません。
そこで、自社の顧客満足度を調べて顧客に対して効率的に集客を行う店舗が増えてきました。また、運営面での無駄をなくし顧客に評価される商品やサービスを企画するうえでも顧客満足度は役立ちます。
たとえばですが飲食店なら、顧客満足度調査から評価の低いメニューは広告排除し、売り上げアップに貢献できる評価の高いメニューのプロモーションに力を入れるということが可能です。
つまり顧客満足度は店舗や企業の売上と密接な関係を持っているデータなのです。顧客満足度の向上=売上げアップという利益を企業にもたらすといえるでしょう。
顧客満足度まとめ
【関連記事】
顧客接点(タッチポイント)とは?接点強化の目的や方法・事例を紹介

先述したように店舗や企業の売上に顧客満足度は大きく影響します。では具体的には、どのような流れで顧客満足度の向上は売り上げ向上をもたらすのでしょうか。
よく顧客満足度ランキングで上位にいる企業は、どの企業も以下のようなメリットから売上への恩恵を受けているのです。顧客満足度向上がもたらすメリットを解説しています。
顧客満足度が高まると、店舗や企業のリピーターが増えていきます。
みなさまもお気に入りのお店やサービスが絶対に1つはあると思いますが、いいサービスを提供する企業や店舗は、人はやはり何回も利用したくなるのです。
リピート回数が増えた結果、1人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益の額が変わるので、売上向上に影響するといえるのです。ちなみに、その利益額を「顧客生涯価値」と呼びます。英語では「Life Time Value」、略して「LTV(エルティーブイ)」と称されています。
マーケティングにおいては、いかにLTVを上げていくかが重要です。そのためには、既存客をリピーターに変えていかなくてはいけません。リピーターは中長期的に企業の売上に貢献してくれる存在だからです。
当然ながら、既存客は商品やサービスに満足していなければ、再びお金を払おうとは思ってくれません。そこで、顧客満足度を参照することが大切になるのです。
さらに、顧客満足度が向上すれば、リピーターの利用頻度が高まって客単価が上がります。
特定の店舗をひいきにしてこなかった浮遊客も固定客に変わっていくため、売上に好影響が出るでしょう。これまではライバル社の商品も購入していた顧客が、以降自社でしか買い物をしなくなることもありえます。
企業にとって新規顧客が増えるのも大きなメリットです。顧客満足度向上が新規顧客を生み出すのは、「口コミ」に影響するからです。
昨今では口コミ評価は絶大な影響をもたらします。少し前の時代とは違い、FacebookやtwitterなどのSNSによって商品やサービスの情報は簡単に拡散されます。
特定の個人の意見が世間から注目され、宣伝となることも珍しくありません。芸能人やモデル、政治家などに多いインフルエンサー(SNS上で影響力を持つ人)がいい例です。
逆をいえば、満足度の低い商品やサービスの悪評も広がりやすく、売上が落ちてしまうリスクも出てきます。
顧客満足度が向上すれば、SNSなどの口コミで高評価が浸透するようになり、商品やサービスが信頼を得ていくでしょう。その結果、評判を聞きつけた新規顧客が獲得できるようになります。
そして、新規顧客がついた後、彼らを固定客に変えていくためにも顧客満足度は役立ちます。一時的に新規顧客が増えても、商品やサービスの質が落ちてしまってはすぐに消費者は離れていくでしょう。
顧客満足度を意識しながら経営することで商品やサービスのクオリティは保たれ、安定した売上につながります。常に企業や店舗が成長し続けていくには、顧客の需要に応える経営が必須なのです。
顧客満足度は企業のブランドイメージにも影響します。
固定客が多い企業は、そもそも世間から良い印象を持たれる傾向にあります。経営が良好であるとか、商品が安全であるといったイメージが浸透することにより、新規顧客の数は増えていくでしょう。また、一度お金を使ってくれた顧客がリピーター化しやすくなり、売上が増えていくのです。そして、企業の中長期的な発展を促します。将来的な成長に寄与する要素として、世間から健全な認知を得ることはとても大切です。
企業のイメージが良くなり、リピーターが増えていくと宣伝効果も期待できます。
お金をかけて広告を制作したりメディアに露出したりしなくても、リピーターが自主的に情報を広めてくれるからです。集客力が高まるだけでなく、広告費を削減できるのもメリットといえるでしょう。
【関連記事】

マーケティングは顧客管理が大切!その重要性と活用方法について
過去に顧客から寄せられた「クレーム」「SNSの口コミ」「アンケート」は、自社サービスがどのように見られているかを知る重要な資料です。
これらの情報を利用して、現在なにが顧客満足度を下げているのかを知ることができます。
以下は顧客から寄せられる意見と、それに対応して改善すべきポイントの一覧です。
ここからはそれぞれの改善方法がどのようなものかについて解説します。
人の入れ替わりが激しい店舗では、それぞれの経験値に差が生じます。
ゆえに店舗には、技術や接客マナーのような経験値を、早い段階で一定の水準まで引き上げることが求められます。
たとえば、一定期間の研修や定期的なフィードバックが重要です。
他にも「過去にあったクレームを共有する」「指示を仰ぐ担当者を決めておく」など、クレームの対応フローをあらかじめ決めておくと、新人でも対処がしやすくなります。
後述する「スターバックス」の事例では、事細かなマニュアルではなく、あえて抽象度の高い価値基準を従業員に浸透させることで、従業員の育成に成功した方法を紹介しています。
商品の改善で重要なポイントは「品揃え」と「品質」です。
商品に対する不満を解消するためには「品揃え」を充実させて、顧客の求めるものをスムーズに提供することが肝心です。
たとえば、在庫管理にAIシステムを活用して過去の取引から、売れ筋の商品のみを多めに発注するような仕組みを作れます。
また、自社で商品開発をしている企業であれば、顧客のニーズを汲み取り「品質」を向上させることが常に求められます。
万が一、欠品商品が出た時の対処法として、取り寄せ可能な日を提示する、または代替え商品を提案するなどがあげられます。
後述する「良品計画」の事例では「新商品のアイデア」や「改善して欲しい商品」を常時募集しており、顧客の声を商品開発に反映させています。
顧客は待たされることや手間がかかることを嫌います。
そこで、サービスが提供されるまでの時間や手間を減少させることで、顧客満足度を高めることが可能です。
「マクドナルド」では、店内に座ったままアプリで商品を注文し、決済できるサービスを提供しています。レジに並ぶ時間と手間をなくし、混雑緩和にもつながっています。
その他「ログインしなければ問い合わせできない」「利用しないサービスがパック料金に含まれている」など、顧客に不利益な仕組みを改善する必要があります。
後述する「ソニー損保」の事例では、企業にとって損になる選択肢をあえて顧客に伝える「顧客ファースト」の考え方を紹介しています。
衛生状態の悪さや、混雑した環境は顧客の不満を高める原因になります。
「忙しい時間であっても清掃する時間を設ける」「什器が壊れていないかを確認する」など、店内の環境を美しく保つ工夫が必要です。
また、顧客や従業員の動線を意識して商品を陳列することで混雑が解消し、人の流れがスムーズになります。
後述する「カルディ」の事例では、通路を広く取りベビーカーを通りやすくすることで、ファミリー層のニーズを取り入れた工夫を紹介しています。
アプローチする層を見誤れば、購入する見込みの低い層に向けて投資をすることになります。
ターゲットを決める、あるいは変更する場合は、投資対効果を高くすることが重要です。
そのためには、自社の商品価値や顧客を調査すると共に、市場調査をする必要があります。
自社製品の価値を理解し購入する層を、見つけて育てることが投資対効果を高める鍵です。
後ほど、顧客と市場のニーズを徹底的に調査・分析したことで「顧客の愛着度」を上げることに成功した「再春館製薬」「ヤクルトスワローズ」「セイコーマート」の事例を紹介します。
企業が利益を伸ばすには、顧客満足度の向上を無視できません。顧客が満足を得られる供給を続けていれば、集客や売上に好影響が及ぶでしょう。
そのため、順調に利益を出し続けている企業は自覚的に顧客満足度を向上させる取り組みを行っています。この段落では、顧客満足度向上に関する施策として、5つの成功事例を取り上げます。
「初めての方にはお売りできません」という強烈なCMで、再春館製薬は知名度を高めました。
一見すると顧客を選別しているように思えるものの、実際にはリピーターを増やすことに成功しています。理由としては、既存の顧客が会社との間に強いつながりを感じられている点が挙げられるでしょう。リピーターは企業から特別感を持たれていると思えるので、進んで再春館製薬の商品を買うようになりました。
再春館製薬は顧客数が頭打ちになるタイミングで顧客調査と分析を行い、1年以上利用している顧客のリピート率が高いとの結論を出しました。そして、リピーターの顧客満足度を高める方向に舵を切ったのです。
具体的には、購入後数カ月の顧客への電話によるアフターケアなどを行い、会社に対して好印象を抱いてくれるような営業活動を積極的に取り入れました。
そのほか、LINEの公式アカウントを使った顧客接点の生み出し方も見逃せないでしょう。顧客が肌トラブルなどの相談をLINEから気軽にできるようなサービスを実施し、反響を呼びました。顧客満足度向上を常に意識している姿勢が、リピーターの愛着をより強いものにしています。
プロ野球チームであるヤクルトスワローズも、顧客満足度調査を基にして運営の立て直しに成功した組織です。スワローズが顧客満足度調査を行ったところ、地方のファンが球場にあまり来ていない事実が発覚しました。東京を本拠地としているスワローズは、地方から遠征するのは敷居が高かったのです。
また、地方のファンクラブ会員は、会員であることのメリットを希薄に感じていたことも判明しました。一方で、ユニフォームなどのグッズ特典はファンから高評価を受けていました。
これらの分析結果を踏まえて、スワローズは地方ファン向けのイベントを積極的に開催し交流を深めていきます。
そして、会員特典を増強するなどの工夫も行いました。こうした施策が実り、2014年から2016年の2年ほどで、会員数はおよそ2.5倍に膨れ上がります。そのうえ、有料となるプラチナ会員の入会数も増加しました。さらに、観戦チケットの売上も伸びて、経営状況が改善されたのです。
コンビニ業界は大手グループのシェアが高いため、地方を拠点にしている店舗は苦戦する傾向にあります。
そのような中にあって、北海道を主戦場にしているセイコーマートは、大手コンビニを抑えて顧客満足度アンケート1位に輝いたこともあるグループです。
セイコーマートの特徴は、北海道民の心情に寄り添う地域密着の経営を行っている点でしょう。セイコーマートは、ライバル店が撤退するような過疎地であっても出店を続けてきました。あくまでも地元に根づく姿勢を見せることで、北海道民からの信頼を得るに至ったのです。
しかも、プライベートブランドが充実していたり、ポイントカードやICカード決済なども顧客から評価されています。
セイコーマートのサービスには、ほかのグループが思いつかないアイデアも少なくありません。こうしたサービスの評判は北海道を超え、全国にも知れ渡るようになりました。北海道民の需要に応える経営体制は、顧客満足度向上についての好例だといえるでしょう。
コーヒーチェーンとして人気のスターバックスも、顧客満足度を意識したサービスで注目されるようになりました。通常、飲食店では細かい接客マニュアルを作成することで従業員の意思を統一させ、安定したサービスへとつなげています。
しかし、スターバックス従業員が共有する「グリーンエプロンブック」では、固定されたマニュアルがありません。そのかわり、「歓迎する」「心を込めて」「豊富な知識を蓄える」「思いやりを持つ」「参加する」の5つが従業員に伝えられています。
従業員はこれらを心がけながら、各店舗で機械的ではない接客を行っています。これにより、特に女性や若年層に爆発的な人気があります。
スターバックスはスタッフの行動をマニュアルで制限するのではなく、ビジョンを共有することで自主的におもてなしを考えさせるようにしました。
また、現場スタッフに権限移譲し、マニュアルだけでは対応しきれない事態も臨機応変に乗り越えています。
こうしたスターバックスの姿勢は顧客の評判を呼び、居心地のいい空間としてリピートされるようになりました。ブランドイメージを高めるためにも効果的だといえます。
保険会社の営業活動でも、顧客満足度は重要なデータです。保険とは加入者がピンチにおちいったときのための契約なので、サービスに信頼性がなければ売上にはつながりません。
そして、保険会社の中でも特に顧客サービスへと力を注いでいるのがソニー損保です。顧客に安心感を与えるようなテレビCMを覚えている人も多いでしょう。
ソニー損保が多くの保険会社と違う点は、契約数や売上ではなく顧客満足度向上に主眼を置いた中長期的な経営戦略を柱としていることです。こうした姿勢が顧客に受け入れられ、結果として収益増加に成功しています。
たとえば、ソニー損保は災害が起こったときに、「保険が下ります」と顧客にメールを送っています。また、低額のプランができたときに見直しを推奨するような連絡も行ってきました。これらのサービスは、企業側の立場からすれば損だといえます。
しかし、顧客目線を徹底することで、信頼を強めてきたのでした。
そのほか、「保険料は走る分だけでいい」というサービスも導入しています。「あまり走っていないのにどうして高い保険料を払わなければいけないのか」といった顧客の声に応えた形です。コールセンターやロードサービスの満足度が高いのも強みでしょう。
ここまで有名企業の顧客満足度向上についての施策を紹介してきました。いずれも、顧客目線に立った施策であることが共通点です。
各企業の取り組みは、経営規模や知名度に関係なく参照できるポイントがたくさんあります。ここからは、自分の会社で顧客満足度向上を図るための心がけを具体的に紹介していきます。
まず、顧客満足度向上のためには「顧客の想像以上の商品やサービスを提供する」ことが大前提です。顧客の想像範疇であれば、決して満足を覚えてもらえるとは限りません。
また、ライバル企業に顧客を奪われるケースも珍しくないでしょう。顧客の想像を超えるには、そもそも自社の商品やサービスがどの程度の期待を受けているのかを調べるべきです。現時点でハイクオリティの商品を提供しているつもりでも、顧客の期待値が非常に高いと想像を超えられない場合が少なくありません。そのうえで、顧客の抱いている期待値を上回ることを目指しましょう。
さらに、顧客が抱いている不満・つまりクレームを聞き逃さないことも大切です。
わずかな不満によって、ライバル社に顧客がなびいてしまう可能性もゼロではないからです。アンケート調査などで顧客の声を確認し、商品やサービスの改善に生かしましょう。
このようにして顧客をじっくり観察すると、自社の課題が見えてきます。現実的に取り組める方法の中で、もっとも効率的なアプローチによって課題解決を試みましょう。そうすれば、顧客満足度は自然と高まっていきます。
顧客満足と同等に重要な指標が「従業員満足度(ES=Employee Satisfaction)」です。
従業員満足度では、企業で働く従業員のやりがいやストレスの有無を数値化しています。かつては、顧客満足度を優先させるあまり従業員満足度がおろそかになっている企業も少なくありませんでした。しかし、両者は無関係でないと発覚してからは、従業員満足度を大切にする企業も増えてきています。
むしろ、顧客満足度を高めるためにまず、従業員の満足感を高めようとする考え方も一般的になりつつあります。
具体例として、ディズニーリゾートは従業員だけが貸し切りで園内で遊べる「サンクスデー」を設定しました。また、現場スタッフが上層部にアイデアを提案する機会が設けられるなど、従業員満足度向上に取り組み、離職率を下げています。
あとは2020年に始まった、新型コロナウイルスの問題もあります。コロナウイルス対策は顧客だけでなく従業員全体を守り満足度を向上させる施策の一つです。
従業員満足度は売上だけでなくコストや作業効率にも影響するので、ストレスのない職場づくりは経営陣が無視できないテーマのひとつです。
顧客のニーズを把握するために有効なツールがCRM(Customer Relationship Management)です。
CRMを活用することで、顧客の情報を的確に管理し、営業やサービス改善に活かすことが可能になります。
顧客満足度を高めるためには顧客の思考や行動を知る必要があります。
今、多様化しているビジネスにおいて、ずっと同じサービスや商品を提供していても顧客に飽きられてしまいます。サービスや商品の改善には顧客が求めているものをちゃんと理解することが必要です。
ニーズを把握し、分析するためにはCRM活用が欠かせません。
【関連記事】
CRM分析で顧客満足度アップ!分析手法や効果的に行うポイントを解説
スマホの普及により、SNSは当たり前のように使われています。顧客とのコミュニケーションツールとしても宣伝媒体としても、スマホで簡単に利用できるSNSは欠かせません。
また、SNSでは次々と新しいサービスが開発されています。経営者や宣伝担当者は新しい情報についてアンテナを張り続け、必要であれば柔軟に導入していきましょう。
もう一つオススメしたいのは店舗アプリの利用です。店舗集客で有効活用できるのが「店舗アプリ」です。
顧客をリピーターに変えていくために有用なアプリの制作サービスであり、メルマガやスタンプカードの代わりとしても人気です。
最後に少しだけですが、顧客満足度向上に役だつ当社のGMOおみせアプリについてご紹介します。
【関連記事】
囲い込みの考え方・メリットや戦略とは?施策例や便利ツールを紹介!
「O2Oマーケティング」(O2O=Online to Offline)を実現するために、GMOおみせアプリは大切な役割を果たします。
O2Oマーケティングとは、オンラインでの宣伝活動をオフラインでの消費活動へと結びつけるための活動です。
GMOおみせアプリでは店舗集客に効果的なサービスがそろっており、各店の特徴に合わせたアプリを作成できます。ここからは、GMOおみせアプリの魅力を述べていきます。
顧客満足度が向上すればリピーターも増えていくのは、ここまでで解説してきたとおりです。そして、おみせアプリを利用すればさまざまな機能で顧客満足度を高められるので、再来店を促進できます。
たとえば、スタンプの発行やランクアップ会員制度は代表例でしょう。顧客の心をつかむための工夫が満載であり、ライバル店に差をつけられます。さらに、ニュースの発信機能によって、イベントなどの宣伝が手軽に行えます。そのほか、クーポンの発行やゲーム販促なども可能なので、顧客の興味を持続させられるでしょう。
顧客が数度の来店だけで飽きてしまわず、何度でも足を運びたくなるように訴求できます。
おみせアプリの主な目的は、商品やサービス、キャンペーンの広告を手軽に行うことです。それだけに留まらず、集客やリピートを促すこともできます。
そして、店舗の情報を絶えず配信し続けて顧客との関係を強化できるので、ヘビーユーザー獲得にもつなげられるでしょう。
おみせアプリを使えば、顧客に対する積極的なアプローチを頻繁に行えます。そのため、来店から間が空いた顧客にも働きかけて、ライバル店に奪われにくくできるでしょう。
そして、アプリを使って顧客データの収集も可能です。客観的な資料が手軽に閲覧できるので、マーケティングの精度が高まります。自店の顧客の傾向がわかれば、的確な宣伝方法を考えられるでしょう。
おみせアプリで確認できるデータは、まず来店履歴です。顧客ごとの利用頻度をチェックし、ヘビーユーザーとしての度合いを判別できます。
次に、クーポンの利用回数や顧客の行動なども把握可能です。キャンペーンの反響をデータ化することで、次回以降のマーケティングに生かせます。
そして、来店頻度の高いロイヤルカスタマーに特別なセールを紹介したり、休眠ユーザーに情報発信したりするなどの機能も役立つでしょう。そうすると、リピーターの来店頻度がますます上がっていき、売上増加を期待できます。
弊社アプリ制作サービス「GMOおみせアプリ」では、リーズナブルで高品質のアプリが制作可能です。導入企業は3,220社/11,100店舗(2025年5月時点)を超え、さまざまな業種の企業や店舗でご利用いただいております。
事例はさまざまであり、チェーンの飲食店や小規模な店舗が集客力を上げるきっかけにもなりました。
そのほか、リピーターを重要視している各種の店舗でもGMOおみせアプリが使われています。
美容室やペットカフェのように、店員と顧客のコミュニケーションが大切な店舗には向いています。また、温泉施設やフィットネス施設、ゴルフクラブのようにサービス内容を詳しく訴求する必要のある場所からも人気です。
観光施設や娯楽施設は割引などがあると再来店しやすいので、おみせアプリのクーポン発行機能が広く利用されています。
企業向けにはGMOデジタルPayもおすすめ!
GMOおみせアプリは、会員証やポイントカードのデジタル化、プッシュ通知による効果的な情報配信など、多彩な機能で集客・販促を強力にサポートします。
GMOデジタルPayは、企業独自の電子マネーやデジタル商品券の発行を支援するサービスです。紙の管理から解放され、業務効率化とコスト削減を実現します。
企業や店舗が売上げを増やすには、顧客満足度向上が非常に大切です。この記事で紹介したさまざまな企業の取り組みでは、いずれも顧客目線を意識していることが判明しました。
まずは、顧客が求めているものを正確に把握しつつ、従業員満足度も同時に高めていきましょう。そして、最新サービスを導入するなどして万全の準備をすれば、顧客満足度向上を集客に結びつけられます。
WEB集客の無料相談・資料請求受付中!
そんなお悩みをお持ちの方は、無料で相談してみませんか?
貴社にぴったりの対策を提案致します。
【参考・参照】
LINEで1.45倍のリーチを生む戦略的なメッセージ配信と顧客満足を創る双方向コミュニケーション
ここで働きたい、やめたくないと感じる、会社と境目のない関係。

2025年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。