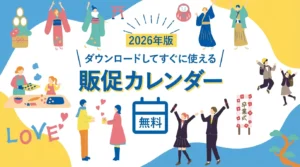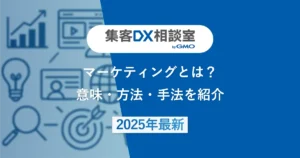2026年の販促カレンダー【無料プレゼント】

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。
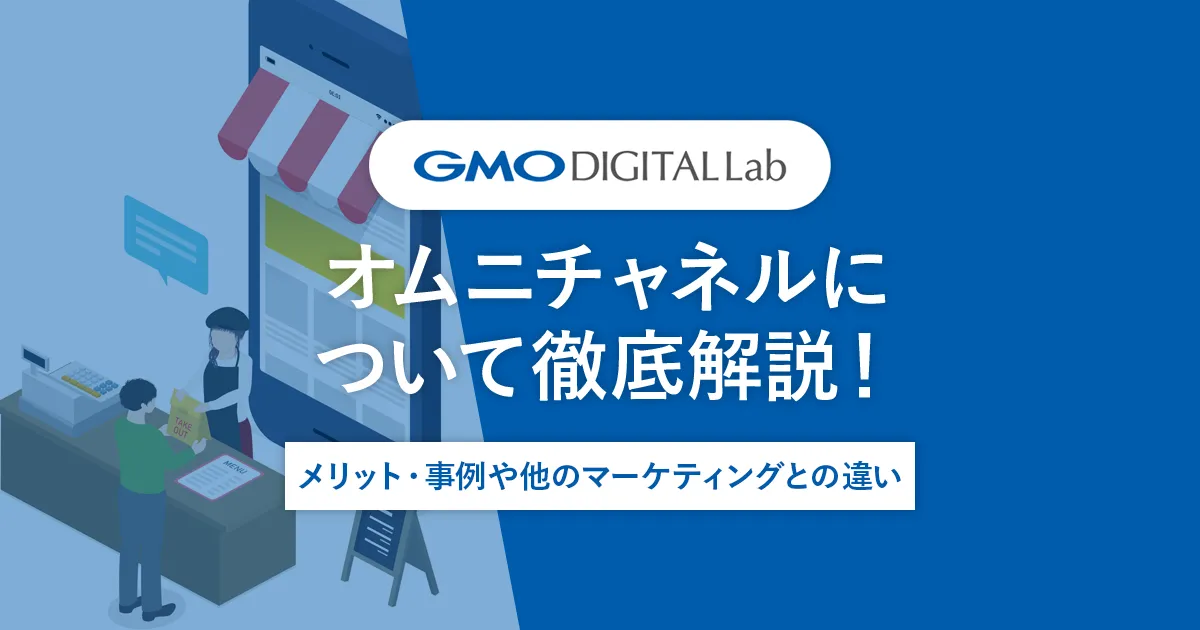

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。
オムニチャネルとはなんなのか、概要やメリット・事例について解説しています。マーケティングの戦略においては「オムニチャネル」を意識した多角的な戦略は非常に重要です。
実店舗やオンラインショップなど、多数のチャネルの融合によりもたらされるメリットは、昨今のマーケティングにおいてより有効性が高くなっています。
オムニチャネルを活用することによりもたらされるアドバンテージはなんなのか、またO2Oや他マーケティングの違い、実際の成功事例についてまとめています。
オムニチャネルとは販売戦略の方法の一つで、実店舗・ECなどの全てのチャネルの垣根をなくし、消費者にアプローチする経営マーケティング戦略です。
企業と消費者の経路である販売チャネルを融合させることで、消費者への最も効果的なアプローチを実現するという考えのもと行われます。
オムニチャネルの手法は、インターネットに加えてスマートフォンが普及したことで、企業に大きなメリットが生じるようになりました。
モバイルデバイスも含めて顧客満足度を向上させてあげることで、よりシームレスなカスタマー体験を提供できます。
企業側からみたときの大きなメリットはチャネル統合による売り上げの向上です。
現在、たいていの企業は実店舗だけでなくオンラインショップや通信販売、ソーシャルメディアなど様々な販売経路を持っています。多様な販売経路の創設に伴い、商品や顧客管理とともに物流などのシステムも顧客の購買につながるよう品質の向上が図られてきました。
それらの要素を融合させることで、顧客がそれぞれのチャネルを自由に使い、消費者自身がより簡単に使える方法を選択して購入することができれば、販売に至る機会損失を防ぐことができます。
つまりオンライン・オフラインの垣根をなくしてしまえば購買率はアップし、売り上げ向上につながるのです
ユーザー側から見れば、オンライン・オフラインに関わらずどのチャネルで購入しても一貫性のあるサービスが受けられるというメリットがあります。
オムニチャネルと、マルチチャネル・クロスチャネル・O2Oとの違いについても解説しましょう。以下の表でまとめていますが、これらを具体的に一つづつ解説します。
| マルチチャネルとの違い | オムニチャネルのようにチャネルごとが連携せずに、独立し活用されている |
| クロスチャネルとの違い | オムニチャネル同様チャネルの連携はしているが、シームレスな統合をしていない点 |
| O2Oとの違い | 基本はオンライン→オフラインという解釈で、オムニチャネルの多角的なチャネルという考えとは異なる |
これを図解するとこうなります。

ちょっと補足していくと、まずマルチチャネルですが、オムニチャネルが生まれるきっかけとなった考え方で、複数の経路を使って消費者が求める商品やサービスを提供するというものです。
ただしオムニチャネルとは違い、存在するチャネルが連携されていないため、消費者から見るとそれぞれが独立したサービスのように感じてしまいます。
それらの販売方法の垣根をなくすためになされてきたのが、クロスチャネルです。
クロスチャネルでは、それぞれのチャネルが連携できるよう、商品管理や販売管理に力を入れ、消費者側から見た場合、それぞれのチャネルに一体感を持たせることができます。
ただ実際のところはそれぞれを横断できる情報管理はされていません。
クロスチャネルの先にあるのがオムニチャネルで、オンライン・オフラインに関わらず、どこを利用してもシームレスな顧客体験を提供するという点で違いがあります。
オムニチャネルと似た言葉でO2Oがよく用いられますが、オムニチャネルとは明確な違いがあります。
O2Oとは、英語で「Online to Offline」と書きます。その名称の通り、オンラインで興味を持った消費者をオフラインである実店舗での商品やサービスの購入に誘導することを目指す考え方で、こちらも図解します。

オンラインサイトから実店舗、もしくはその逆という解釈になり、あくまでの購入を促すための送客というが目的で、多種多様な販売チャネルから消費者を取り込むオムニチャネルとは異なります。
インターネットやスマートフォンが普及したことで、それぞれのサービスが独立しているマルチチャネルの手法では販売の機会損失が発生することが多くなりました。
その要因となったのが「ショールーミング」です。
ショールーミングとは、消費者がある商品やサービスを購入しようとする場合、店舗に来店して商品を見て回るものの購入には至らず、SNSや口コミの評価、価格設定の調査などを行い、最終的にはオンラインなど他のチャネルで購入するという消費行動です。
そのため、企業側では販売チャネルごとの売り上げに着目するというよりも、消費者の購買意欲が高まったタイミングを逃さずに販売できる仕組みであるオムニチャネルの必要性が増しています。
オムニチャネルをマーケティングに活かし成功させた事例を二つ紹介させていただきます。
オムニチャネルは小売業界に革命をもたらしていますが、スーパーやショッピングセンターなどを運営するある大手企業では、消費者それぞれに寄り添ったアプリやデバイスを提供することで、買い物の利便性を上げ、売上につなげています。
例えば売り場に設けられているPOPなどに起動したアプリをかざすと、その商品を使ったレシピが表示されます。
消費者は献立のヒントを得られますし、料理を作るために足りない材料も併せて購入することで、消費者・販売店それぞれがWinWinの関係を築くことができています。
また、自社ブランドの商品を企画・製造から販売まで手掛けるある専門小売企業で提供するアプリは、商品に関する情報とともに在庫検索ができるなど様々な機能を持ち合わせているため、顧客は好きなチャネルから購入することができます。
さらに、このアプリを使用している人が店舗の近くに来るとマイルがたまり、各消費者のニーズや時間帯にマッチしたクーポン情報も届きます。
また、買い物時にレジにアプリをスキャンしてもマイルがたまるため、来店意欲が促され、その結果として売上アップにつながっています。
こちらで紹介した事例以外にも、アプリを活用したマーケティングは企業においてトレンドになっています。
オムニチャネルは、成功するための特定の方法は存在しません。
それぞれの企業とそれを取り巻く消費者のニーズにマッチしたものでなければ成功には至りません。
それで、目指すべき方向性を検討することが大切になります。
ただし最適なオムニチャネルを構築するために必要な販売経路が足りない場合は、オンライン・実店舗を含めて用意することが必要ですし、顧客のニーズを的確にとらえるための顧客・販売管理システムの導入と連携は不可欠です。
そうすることで顧客の購入に至る動向を理解することができ、どんなことがきっかけで購入するのかがわかれば、用意すべきアプローチの形が見えてきます。
また、オムニチャネルには成功はあってもゴールはありません。
それで、オムニチャネルを実現させた後の効果のほどを検証・分析する仕組みは大切ですし、また様々な販売チャネルと消費者の接点に存在するサービスの質を上げていくことも顧客離れを防ぐためには不可欠です。
オムニチャネルの強みは多角的なチャネルにより顧客満足度を向上させてあげることで、よりシームレスなカスタマー体験を提供できることです。
近ごろはカスタマーサクセスという言葉もありますが、優良な顧客体験は利益を創出するのです。
マーケティングにおいてオムニチャネルの強みを生かし、より店舗や企業の発展に活かせるようにしていきましょう。
またオムニチャネルを実現するツールとして、店舗アプリはよく用いられるツールです。弊社のGMOおみせアプリもオムニチャネルの展開には有効に活用できます。

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。