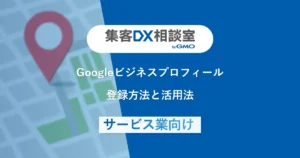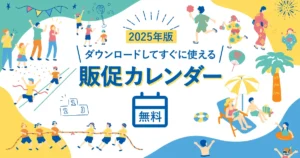2025年6月はじまり販促カレンダー【無料プレゼント】

2025年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。


2025年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。
スマートフォンが普及して、いつでもインターネットに接続できる現代では、オンラインでのサービスが増えており、その中で誕生したマーケティング手法が、OMOです。
今回は、OMOについて言葉の意味・概念や、実際のOMO施策事例・OMOマーケティングの実践方法など、ビジネスに活用できる知識をご紹介します。
このような方におすすめです
OMOとは、オンラインとオフラインを融合しユーザーに体験を提供するという概念です。
「Online Merges (with) Offline」を略した言葉であり「オンラインとオフラインの融合」を意味します。
この概念が生まれたのは比較的新しく、2017年9月ごろ、元GoogleチャイナのCEOであり、現シノベーションベンチャーズの李開復(リ カイフ)が提唱して広まった言葉になります。
OMOを正しく知るためには、マーケティングにおけるオンラインとオフラインの違いを正しく理解することが重要です。そこでOMOについて詳しく解説する前に、まずはオンラインとオフラインとは何かについて確認しましょう。
| オンライン | オフライン |
|---|---|
| パソコンやスマートフォンといったデバイスがインターネットに接続されている状態 | オフラインとは、パソコンやスマートフォンといったデバイスがインターネットに接続されていない状態 |
| 「line=インターネット」に「on」している状態をイメージすると理解しやすい | そもそも「off」は「〜から離れて」や「〜から外れて」という意味の言葉であることからもオフラインの使い方が想像しやすい |
| 現在では「ネット上のもの」という意味で使われる場合も | インターネットに接続されていない状態を意味するだけではなく、現実世界に存在するもののことを指す場合も |
| インターネット上で買い物ができるオンラインショップのオンラインは、ネット上のものという意味 | |
| オンラインはデバイスがインターネットに接続されている状態や、ネット上のものという意味の言葉 | オンラインの対義語であるオフラインはインターネット上のものではなく現実世界のものを指す言葉になった |
OMO (Online Merges with Offline)は、オンラインとオフラインの取引を結びつけることで、顧客により豊富な体験を提供することを目的としたマーケティング手法です。
これは、オンライン上での情報収集や予約をしてから、実店舗での受け取りや支払いができるといった形で、オンラインとオフラインの取引を結びつけることを意味します。
OMOを用いて、オンライン上とオフライン上でどのようなことができるかを簡単な表にまとめました。
| 顧客がオンライン上での情報収集や予約 →実店舗での取引を促進する | 顧客がオンライン上での購入を検討している →実店舗での体験をプラスすることで、購入意欲を促進する |
OMOを活用することで、顧客により豊富な体験を提供することができるだけでなく、オンラインとオフラインの取引を結びつけることで、顧客の購入意欲を促進することもできます。
例えば、 電子商取引サイトで商品を見ている消費者が、実店舗での商品の見せ方や試着をすることができる、といった形で、オンラインとオフラインの取引を結びつけることで、顧客により豊富な体験を提供することができます。
このOMOの考え方は、中国において幅広く浸透していますが、OMOの中心にあるのはスマートフォンです。
スマートフォンでの利便性向上のためOMOの考え方が取り入れられているといえるでしょう。
例えば大きなショッピングモールはもちろん、地方の市場の小さな屋台までスマホ決済が取り入れられています。
OMOのメリットはスマートフォン端末さえあれば買い物が楽にできるということ。企業側からすると顧客の購買意欲を高め売り上げ向上につなげます。
これら全てがスマホ決済で可能になりました。つまり顧客は場所にかかわらず、さまざまなお金のやり取りをスマホ1つで行うことができるのです。
まさしくOMOの考えでオフラインとオンラインがうまく融合し、顧客の利便性に結びついているといえるでしょう。
中国の大手Eコマース企業は、自社が展開するスーパーマーケットで販売する商品の値札にバーコードを付け、それをアプリで読み取ると、商品の詳細情報や商品を使ったレシピを確認できるようにして客の利便性を向上させています。また、買いたい商品をあらかじめアプリで読み取ってレジで表示させれば、すぐにキャッシュレス決済できるので、レジでの待ち時間の削減につながっています。
OMOは中国だけでなく、アメリカや日本など世界各国でも積極的に進められています。
OMOは日本でも活用事例が増えています。例えば、大手コーヒーチェーンでは味覚診断機能があるアプリを開発し、いくつかの質問に答えるだけで味覚を判断して、好みのコーヒーのタイプについての情報を客に提供します。このアプリは、自分のコーヒーの好みがわからずオーダー時に迷っていた人に好評で、商品の満足度にもつながっているようです。
詳細については後述します。
以下の施策を活用することで、顧客により豊富な体験を提供することができるだけでなく、オンラインとオフラインの取引を結びつけることで、顧客の購入意欲を促進することもできます。
OMOにより待ち時間や手続き時間の削減、複数店舗の在庫の一元管理、ECサイトでの購入などが可能になります。以上によりユーザーにストレスのないスムーズな顧客も提供できるようになり、新規顧客やリピーター獲得も期待できるでしょう。
ここからは、OMOの具体例をご紹介します。
オンライン上で予約をすることで、実店舗での受け取りや支払いができるようになります。
オンライン上でQRコードをスキャンすることで、実店舗での特典や割引が受けられるようになります。
オンライン上で購入をすることで、実店舗での受け取りをすることができるようになります。
オンライン上で試着体験をすることで、実店舗での試着体験をすることができるようになります。
オンライン上でカスタマイズをすることで、実店舗での受け取りをすることができるようになります。
OMOとO2Oとオムニチャネルの二つを比べるとその考え方には違いがあり、それぞれの違いを以下の表にまとめさせていただきました。
| 主軸 | 概要と目的 | |
|---|---|---|
| O2O | 企業 | オンラインからオフラインへの送客・またその逆をし購買を促す |
| オムニチャネル | 企業 | オンライン・オフラインを融合し、多角的なチャネルのアプローチで接点を持ち購買を促す概念 |
| OMO | 顧客 | オンライン・オフラインの区別をせず、一体化し利便性を高め体験を届ける |
これらが違いになりますが、わかりづらい方もいると思いますので少し補足させていただきます。
O2Oとは「Online to Offline」を略した言葉であり、オンライン上の情報などにより顧客の購買意欲を高め、オフラインの実店舗で消費活動を行ってもらうことを狙うマーケティング手法です。
たとえばECサイト上でクーポンを発行し、それをオフラインの店舗での購買時に活用してもらうというようなものです。そしてO2Oはオム二チャネルの中に含まれる概念の一つです。
【関連記事】
O2Oを実践!O2Oの意味とマーケティング活用の7つの施策とは
オムニチャネルは、オフライン・オンライン問わず、顧客へ多角的にアプローチして接点をもつことにより、顧客の購買意欲を高め売上をアップさせる方法をさします。
オムニチャネルで指すチャネルの例は以下のようなものがあります。
さまざまなチャネルを複合して、購買を促すマーケティングの考え方になります。
まとめていきますが、O2Oはオンラインを活用しオフラインの購買を促進するというマーケティング戦略であるため、オンラインとオフラインの区別ははっきりとしています。
再度お伝えさせていただくと、オンラインとオフラインを「区別するか・しないか」、目的、また主体が違いです。
オムニチャネルもオンライン・オフラインを併用する手法ではあるものの、O2Oと同様2つの区別は明確です。
対してOMOはオンラインとオフラインを融合させつつ、顧客の購買意欲をアップさせるだけでなく、さまざまな体験をさせることを目的としています。OMOは買うという行動を促進するだけでなく、カタログ閲覧から購買・決済に至るまであらゆる体験を元に構築します。
OMOは企業を主軸とするのではなく、顧客を主軸とし、顧客目線での利便性を追求した概念であるということも抑えておきましょう。
日本におけるOMOは世界に比べてあまり進んでいません。背景として大きいと考えられるのは、日本の市場はオフライン店舗が未だ多くの割合を占める点です。
オンラインを利用してさまざまな情報を発信しながら、オフライン店舗への集客や購買を狙う方法は一般的になりつつありますが、オンラインとオフラインはまだはっきりとした区別が付けられています。
キャッシュレス支払いの促進などにより、スマホ決済などを行える店舗も増えてきてはいますが、まだOMOが広がっているとまではいえない状況です。
ただし、オンラインをマーケティング戦略としてか活用することが欠かせないという認識は多くもたれているため、これからいかにオンラインとオフラインを併合していくが重要となってくるでしょう。そして、2つの垣根を取り去ろうと、さまざまな事業・社内の改革を行っている企業も増えています。
例えば、これまではオンラインとオフラインに関し、社内の担当部署もわかれている状況だったところ、部署同士の連携を密にしお互いの業務領域を把握しあったり、あるいは部署をまとめたり、企業側もOMOに取り組むため改良を行っているケースが見られます。
日本はすでに完成された便利さがあるがゆえ、利便性に関し現状で満足している雰囲気があります。
ただし、中国やアメリカなどを拠点とする大企業などを中心に、OMOが急速に進化をみせているため、置いて行かれないよう世界と足並みを揃えるためには、日本の中でもOMOに関し積極的に取り組んでいかなければならないと言えます。
ヨーロッパ各国など日本と同じような状況を抱えている他国の動きも注視しつつ、日本の現在の市場とマッチするようなOMOの仕組みを考えていく必要があるでしょう。
マーケティングで高い効果を期待できるOMOもうまく活用しなければ効果は得られません。
そこでOMOを活用する際は以下のポイントを意識しましょう。
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
まずは集客経路を複数用意し、それぞれに合わせてユーザーのタッチポイントを作りましょう。例えば、オンラインであればICサイト、SNSの活用、購入履歴やアクセス履歴などのデータ分析をしたり、オフラインであればチラシや実店舗での営業活動による集客が可能です。
集客経路を一つに絞るよりも複数用意しておくことで、より多くの顧客にアプローチできます。
ユーザーがオンライン、オフラインを自由に選べる顧客体験を提供することも大切です。
なぜなら、ユーザーによってオンラインとオフラインのニーズが異なるからです。
オンライン・オフラインのデータからユーザー情報を分析し、それぞれに最適な施策を検討、実践しましょう。
オフライン・オンライン問わないユーザーのデータ管理も大切です。なぜなら、OMOはオフラインとオンラインの双方から顧客データを収集する必要があるからです。
双方のデータを一元管理し、顧客に合ったアプローチをすることで、効率的なマーケティングが可能になります。
2020年からのコロナウイルスによって、デジタル化は世界で急速に加速し、さらにOMOが注目されました。
日本では従来あまり進んでいなかったOMOが、大企業によりこぞって実現されつつあります。
トレンドとして、非接触決済やスマートフォン、オンラインの顧客接点への注目がさらに高まったことにより、今までとチャネルの役割が大きく変わりました。
企業にとっては売り上げが伸びたECを活用することが必須になりましたし、実店舗はリアル体験を提供する場として重要性が高まっています。
今までは実店舗で販売して売り上げを伸ばすということに着目されましたが、今は実店舗で体験を提供し、売り上げはオンラインで作る時代になりつつあります。
品質もよく、魅力あふれる商品が並ぶ日本において、顧客が求めているのはもはやモノだけではありません。入手時の状況や場所、方法といった買い物体験が価値となり、選択の理由となっているのです。顧客との接点が多様化し複雑になっている中、オンライン・オフラインの境目をなくし、顧客の心をつかむOMOの施策はますます拡大していくでしょう。
ここでは業種ごとのOMO施策事例を紹介します。戦略的にOMOを取り入れた事例をまとめました。
アジア圏最大手の中国企業アリババが運営するスーパーには、オンラインビジネスを先進的に進めるこの企業ならではのさまざまな工夫がなされています。
例えば、実店舗においては品揃えを豊富にしたり、生け簀や食材をすぐに調理してもらえるイートインスペースを設置したり、衛生面の整備に力を入れたり、環境作りを行っています。
加えて、アリババ系列のスーパーのアプリを利用すると、スーパーで販売されている食材が運ばれてくる過程を見られたり、店舗で販売している食材を使用したレシピの提案や必要な商品のまとめ購入を行えたり、さらに便利なサービスを利用することができます。
つまり、顧客はオフライン・オンライン双方を活用しながら、便利な環境でショッピングを楽しめるということです。
モバイルペイメントを利用したスムーズな支払いや、一定範囲内への配達サービスなどが、さらに顧客の満足度をアップさせています。
小売業の事例として紹介したいのが、言わずと知れた世界的大手通販サイトであるアマゾンが、アメリカに設置した無人レジのコンビニ、Amazon Goの事例です。
店舗の入口でスマホ認証を行い入店した後は、商品を手に取ったり戻したりする動きを、店内のセンサーが感知しアプリ上に計上、退店時にゲートをくぐることで自動的に決済が行われます。
これにより、会計のためにレジを通る手間や時間がなくなり、スピーディーでストレスフリーなショッピングを楽しむことができるのです。
オンラインとオフラインが絶妙に融合する、まさにOMOらしい仕組みだと言えるのではないでしょうか。
OMOを取り入れ顧客満足度と自社双方の質を高めていると有名な、中国の大手保険会社の平安保険(PING AN)の事例も取り上げておきましょう。
平安保険は、中国国内で最も大きな保険グループの1つ。アプリを活用したOMOを積極的に行っています。
そして中でも評価が高い施策が、アプリで地域において質の高い医療を提供する医療機関を調べ、予約などまで行える施策です。
医療機関の質のバラつきが激しい中国において、大きな話題を呼びました。
また、このアプリは平安保険の顧客でなくても利用できるところが大きな特徴です。アプリではポイントを使用することで、医師とチャットが行え相談や質問などをすることができますが、ポイントを貯める方法がウォーキングなので、特別な条件や課金は必要ありません。
このような、自社の顧客であるか否かに関わらない幅広いサービス精神が、結果平安保険の名を高めることになっています。顧客は平安保険に信頼を寄せ、自社のほかの商品にも興味を持ち始めるでしょう。
また、平安保険はアプリで得た利用者の情報を元に効果的な販売促進を行え、相互にメリットを享受できているのです。
OMOで最も重要なカギを握っているツールがアプリです。
前項の事例でもご紹介した通り、アプリというスマートフォンに密接なプラットフォームを活用することで、OMOをよりさまざまなフィールドに広げていくことが期待できます。
今はスマートフォンも普及し、生活の一部にスマートフォンが入り込んでいますよね。
アプリには気軽に起ち上げられるカジュアルさやコンテンツの利用のしやすさなど、オンラインとオフラインをつなぐOMOにマッチする特性と機能が豊富です。
実店舗とオンライン・ECサイトを行き来して商品の購入が行われることが多くなっているため、これらをアプリとうまく融合させることが大事です。そうすれば、より幅広いマーケティングが実現できOMOの促進にも繋げられるでしょう。
自社のアプリを開発するには2つの方法があります。
どちらの方法にしろ、自社の事業をアプリとうまく連動させOMOを推進していくためには、アプリをどのように利用して欲しいか、顧客目線をしっかり取り入れながら設計することが重要です。
OMOの各事例でのアプリの活用方法などを参考にしながら、自社のサービスをアプリとどのように連動させていくかを検討し、OMO促進に活かしてみてはいかがでしょうか。
\ OMO機能も! /
OMOを取り入れることで、オンラインとオフラインの区別に関係なく、顧客の体験や消費活動のバラエティを増やし質を高めることができます。そして結果それが企業の売上アップや事業の拡大などに繋がっていきます。
ぜひO2Oやオムニチャネルの取り組みから得たことも活かしながら、OMOへの挑戦を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

2025年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。