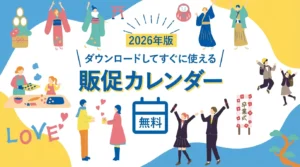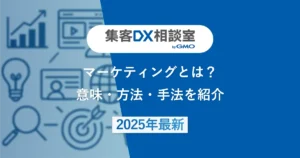2026年の販促カレンダー【無料プレゼント】

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。
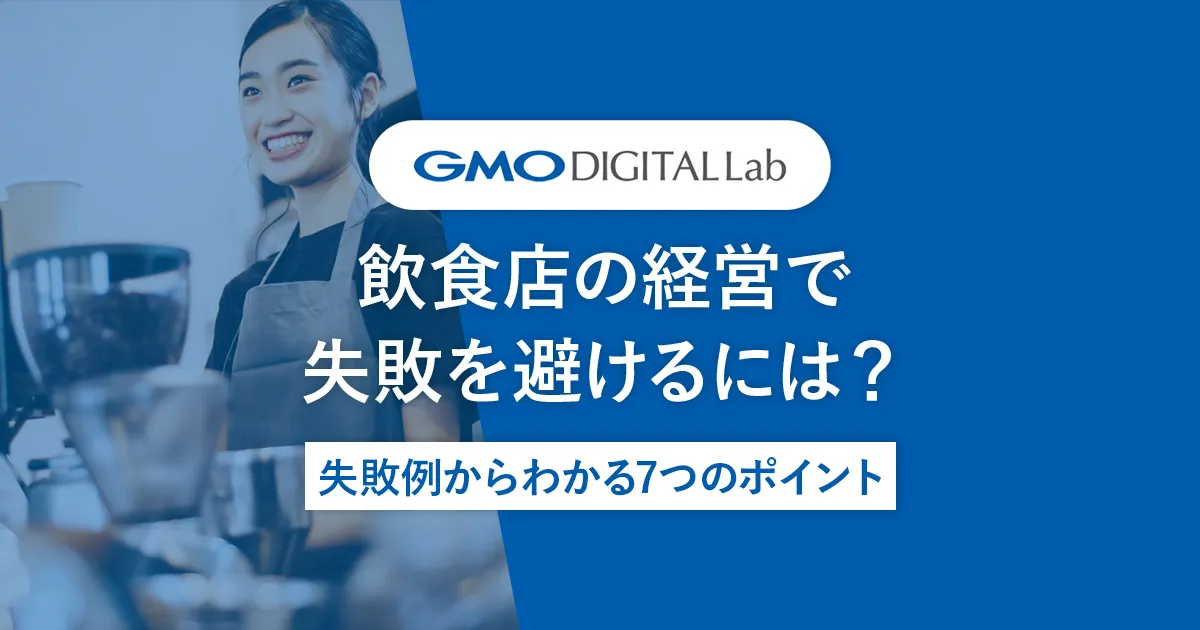

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。
飲食店経営を始めても閉店や廃業するケースはたくさんあります。多くのライバルが存在するなかで飲食店を成功させることはなかなか難しいのです。
それでは、どうして飲食店経営の失敗例は多いのでしょうか。
それらの失敗例から「なぜ失敗してしまったのか」「失敗しないためにはどうしたらよいのか」など、学べることはたくさんあります。
そこで、今回は飲食店の失敗例から学べる7つのポイントについて紹介していきたいと思います。
≪この記事はこんな方にオススメです≫
飲食店経営に失敗して、最終的に閉店や廃業に追い込まれるケースは少なくありません。
それでは、失敗してしまう原因や理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
飲食店を始めたいと考えている人はたくさんいて、毎年、続々と新規参入者が現れます。
どのような地域であっても需要があるのが飲食店であり、近所にライバル店が出てくるのは避けられないでしょう。したがって、ライバル店と顧客を取り合う状況となって、競争にさらされることになります。
その競争に負けてしまえば、最悪の場合、閉店や廃業に追い込まれてしまう可能性もあります。
そうならないためにも「自店のセールスポイントは何か」を明確にして他店との差別化を図ったり、来店してくれた顧客の満足度を上げてリピータを増やす工夫が必要です。
【参考・参照】
たとえば脱サラして飲食店を始める場合には、これまでお店の経営をした経験がないケースも多いのではないでしょうか。十分な経営ノウハウがない状態で開業した場合、はじめのうちはなかなか集客できず、戸惑ったり悩むことも多いでしょう。
また、飲食店以外のお店を経営していた経験があっても、飲食店には独自のノウハウが要求されるため苦労する可能性もあります。
しっかりとした知識を持っていない状態で飲食店経営を始めるのはリスクがあります。
飲食店に限りませんが、たとえば事前に必要なセミナーに参加して経営に関する知識を増やしたり、他の経営者から知識やヒントを得たり、前準備をしっかりしておきましょう。
飲食店経営を進めていくとさまざまな問題に直面する機会があり、そこで適切な対処ができなければ閉店に追い込まれてしまいます。
経営の問題については、自分一人の力で解決するのには限界があって、誰かに頼るべき場面があるものです。
そんなときに誰も相談相手がいないと、自分ですべてを決めることになってしまい、時には誤った選択をする可能性があります。誤った道を選択しても誰も指摘してくれなければ、危機的な状況に陥ってしまうのです。
そのようなことを防ぐためにも、同じように店舗経営をしている方とのつながりを定期的に持つように心掛けたり、必要であればコンサルタントや税理士などのプロに頼ることも考えてみると良いでしょう。
飲食店経営のためには、物件の契約をして、店内の環境を整えて、食材を調達するなど、さまざまな費用が発生します。お店のPRのために広告宣伝をしたり従業員を雇ったりするなど、必要な費用は多岐にわたるのです。
そのため、まとまったお金が必要となるのですが、資金調達に苦労するケースは珍しくありません。
たとえば、融資の申込みをしても審査に落ちてしまうこともあります。資金調達に遅れてしまったために、開業できなかったり廃業することになるケースもあります。
夫婦や家族のみで経営している飲食店もあるのですが、多くの場合には従業員を雇う必要があります。しかし、求人広告を出したとしても、スムーズに人が集まるとは限りません。
飲食店関連の求人はたくさん出ているため、他店舗よりも魅力的な条件で求人を出さなければ、応募者が集まりにくくなります。
また、仮に採用したとしても、すぐに辞めてしまうケースもあるでしょう。十分な人手が集まったとしても、いつ辞めてしまうのか予想することは難しく、安心できないこともあるかもしれません。
従業員に長く働いてもらうために、やりがいを感じてもらえる環境を提供することも大切なポイントと言えます。
飲食店がうまくいかない理由のひとつに、売り上げが不安定なことがあります。なぜなら、飲食店では使う食材の値段が天気や流行によって変わってしまったり、人気のないメニューがあると売り上げが減ってしまうからです。
例えば、天気が悪くなって食材の値段が上がったり、流行が変わって人気のないメニューになった場合、売り上げが減ることがあります。
だから、飲食店は売り上げが安定しないので、経営が難しい業種といわれています。
飲食店で働く人は、長時間働かなければならないことが多いです。その理由は、昼と夜の2回にわたって営業を行うことや、料理を作るために仕込み作業が必要になるからです。
たとえば、ランチとディナーでメニューが違うお店もあるので、それぞれの時間帯に合わせて料理の準備をしなければなりません。そのため、働く時間が長くなってしまうことがあります。
また、スタッフのシフトを調整するのが難しく、管理するのが大変なこともあります。このため、飲食店の経営がうまくいかなくなることがあります。
飲食店経営で失敗するリスクを軽減するポイントをいくつかご紹介します。
飲食店を経営する場合、ただ美味しい料理を提供するだけでなく、資金管理やマネジメントの知識も必要です。料理が美味しいだけでは、経営が上手くいかず、失敗する可能性があります。
数字を把握し、現状を分析し、課題や改善点を見つけ、売上を伸ばすための施策を考えることが大切です。飲食店を経営するには、料理のスキルだけでなく、経営についての知識も身につけましょう。
最初にコンセプトを定めてから、それにしたがって飲食店の経営を進めていくことが多いでしょう。
しかし、経営を始める前に予想していたのと実際に始めた後では状況が大きく異なり、途中で開店当初のコンセプトでは上手くいかないことに気がつく場面も出てくるかもしれません。
最初のコンセプトに固執しすぎてしまうのは失敗しやすい原因となります。途中で方向性を変えるのは勇気のいることで、悩んでしまうことは多いですが、コンセプトに問題があることが分かったならば再調整するのを恐れてはいけません。
いざというときには、思い切った決断をすることが求められます。
飲食店の経営は、決して自分たちの力だけで成功するものではありません。
特にお店で扱う食材の取引先・仕入先との関係は大切にしましょう。信頼関係を築くことができないと、場合によっては途中で契約を打ち切られてしまうかもしれません。食材の仕入れが滞ってしまえば、飲食店の経営をストップしなければいけません。
それを避けるためには、取引先に感謝をして良好な人間関係を築くための努力をしましょう。クレームを入れるときだけ連絡するのではなく、定期的にコミュニケーションを取ることは大切です。
飲食店にとって人手不足の問題は常に頭を悩ませることで、スタッフの人材管理や教育は重要です。「この店」で働き続けたいと思わせることができれば、辞めていく人を減らせるでしょう。
人材管理ではシフト管理が重要で、特定のスタッフに大きな負担がかからないようにします。休みたいスタッフがいれば、できるだけ要望を叶え、シフト調整に対応しましょう。
また、スタッフ教育に力を入れ、サービス向上を実現させて、顧客の満足度を上げることも大切です。スタッフ教育では、主に調理と接客が重要で、店舗のみでなく顧客の利益につなげることを目的として行います。
ただ漠然と飲食店の経営を続けるのではなく、常に分析して、利用客の求めているものを探ることは重要です。たとえば、アンケートを実施して集めた回答を分析してみる方法があります。
そのほかにも店舗用にSNSを開設し、ユーザーからのコメントなどを参考にしてみるのも良いでしょう。
経営において自分の意見を押し通すのではなく、できるだけ周囲の意見に耳を傾け、客観的な視点を取り入れることも重要です。
より良い店舗運営を実現させるために、幅広い意見を集めましょう。
【参考・参照】
店舗・企業のSNS集客担当者必見!SNS活用上手な使い分け方
飲食店を経営する上で、ターゲットを明確にし、価格帯や店の雰囲気をそのターゲットに合わせることもポイントです。
ターゲットを絞り込む際には、年代や性別、趣味などを詳しく設定し、そのターゲットのニーズを理解することが大切です。適切な価格帯や店の雰囲気を設定することで、ターゲットを魅了することができます。
また、ターゲットに合わせたエリアを選択することで、ターゲットが来店しやすい環境を整えることができます。ターゲットの属性から、最適なエリアを選ぶことが重要です。
確かに広告宣伝を活発に行なっている飲食店は、客がたくさん集まり、売上が伸びやすいです。
しかし効果的な広告宣伝ができなければ、逆効果となる可能性があります。たとえば、一人当たり200円の広告費をかけて集客したのに、利益が100円しかでないのでは本末転倒となってしまいます。
費用対効果を重視した広告宣伝をすることを心がけ、定期的に広告の方法を見直しましょう。
【参考・参照】
これから飲食店の経営を始めるならば、これまでの内容を踏まえたうえで開業しましょう。ここからは、飲食店の開業や経営を始める際の具体的なステップについて説明します。
調査時の情報です。
実際にお店を開業するまでには、やるべきことがたくさんあります。一つひとつ確実にこなして開業に結びつけましょう。
成功している飲食店には、それぞれ明確なコンセプトがあるものです。
どのくらいの規模でどんなテーマのお店にするのか、ターゲットは誰なのか、どんな商品をどのくらいの価格帯で提供するのかなどを明確にしておきます。
利用者のニーズに合った魅力的なコンセプトを作り上げることが大切です。
飲食店を始める際に希望する場所があったとしても、そこに都合のいい物件があるとは限りません。
希望通りの立地や物件を探すのは思ったより時間がかかるケースがあるため、期間に余裕を持って探し始めたほうがよいでしょう。
コンセプトに合った物件を見つけられない場合は、コンセプトの見直しをするケースもあります。
飲食店を始めるためにはまとまった資金が必要となり、融資を受けるならば事業計画書の提出が求められます。
きちんとした事業計画を立てて、長期的に安定した利益を得られることを説得しなければいけません。
そのための資料として事業計画書を作ります。また、融資を受けない場合でも、飲食店の経営を成功させるために、事業計画を綿密に立てておくことは重要です。
融資を受ける場合は、事業計画を立てて、それを事業計画書としてまとめたならば、金融機関に融資の申込みをしましょう。
公的な融資制度や補助金・助成金などもあるのですが、これらを利用する場合も事業計画書は必須です。
資金調達には、自己資金を事前に用意しておく、親類や知人から借り入れるなどの方法もあります。
希望にあった物件を見つけられても、そのまま飲食店として使える状態にない場合が多いものです。
そこで、店舗設計をして、内外装工事をしてもらう必要があります。
店舗設計は、予算と相談しながらコンセプトに基づいたものにしましょう。このときに、厨房用具や食器、テーブル、椅子などの備品も揃えます。
飲食店の営業において、オペレーションに関するルールを定めておくことは大切です。
たとえば、接客や調理のルールをマニュアルにまとめておきます。それにしたがって、スタッフの教育や研修を実施する必要もあるでしょう。
また、人材確保のために前もって求人を出す必要もあります。社員やアルバイトの募集をして、面接を行い、ふさわしい人材を選定しなければいけません。
飲食店は官公庁に申請して認められなければならず、開業に伴うさまざまな手続きが存在します。
保健所や消防署、警察署、税務署などにそれぞれ必要な届け出を行い、届け出の期限が決まっているものもあるため、遅れずに申請を済ませましょう。
ここまでのすべての準備を終えれば、飲食店を開業することができます。
飲食店の開業にあたっては、取得しなければならない資格と決められた手続きがあります。とはいえ、どちらも決して難しいものではありません。
飲食店開業において最低限必要な資格は食品衛生責任者と防火管理者です。
食品衛生責任者は、飲食店の各施設に一人設置しなければいけません。保健所に対して食品衛生責任者の届け出が求められます。食品衛生責任者の資格は、都道府県の実施する講習会に受講すれば1日で取得可能です。また、すでに調理師や栄養士などの免許を持っている場合は、自動的に食品衛生責任者を取得できます。
防火管理者は、収容人員が30人以上の飲食店において選任する必要がある資格です。したがって、小規模な飲食店の場合は、防火管理者を用意する必要はありません。収容人員が30人以上で、延床面積が300平米以上の場合は甲種防火管理者、300平米未満の場合は乙種防火管理者が求められます。防火管理者になるためには、1~2日の講習会を受講すればよいです。
調理師免許については、所有者がいなくても飲食店を開業することはできます。ただし、調理師免許があるほうが、一定の技能や知識を有する証明となり、お店のアピールポイントとなるでしょう。たとえば、調理担当のスタッフを雇う際に、調理師免許を条件に設定して募集するケースがあります。
飲食店の営業を始める際には、たくさんの手続きをすることが求められます。
保健所に対しては、食品営業許可申請を店舗完成の10日ほど前までに行う決まりです。
消防署に対しては、収容人員が30人を超える店舗の場合に防火管理者専任届を提出します。また、火を使用する設備を設置する際には、設置前までに消防署に届け出なければいけません。
個人で開業する場合は、税務署に開業届を提出します。従業員を雇う場合には、労災保険や雇用保険、社会保険などの加入手続きをそれぞれの官公庁で行いましょう。
新型コロナウイルスの影響で、飲食店のビジネス戦略は大きく変わりました。成功するためには、時代に合わせた経営戦略が必要です。以下に、今後の飲食店に関する展望を紹介します。
外食需要が減少しているため、自宅や職場で食事を楽しめるフードデリバリーサービスやテイクアウトサービスが需要が高まっています。
これらのサービスを提供することで、売上を増やすことができます。特に、フードデリバリーサービスは自宅で食事を楽しみたい人に人気があります。各フードデリバリーサービスを活用し、ニーズに合ったサービスを提供しましょう。
近年、インターネットを利用する人が増えているため、オンラインサービスを提供することも重要です。例えば、予約システムやECサイトでの販売が挙げられます。
特に、ECサイトで料理を販売し、その商品を気に入ってもらえると実際に店舗に足を運んでくれる可能性があるため、ECサイトも活用しましょう。
QRコード決済やクレジットカード決済など、キャッシュレス決済を導入することもおすすめです。
新型コロナウイルスの影響で、非接触決済が急速に普及しています。複数のキャッシュレス決済に対応し、顧客のニーズに応えるようにしましょう。
【関連記事】
飲食店向けのアプリでどんなことができる?できることや利用シーンを徹底解説!
飲食店アプリ成功例とO2Oマーケティング!売上アップの秘訣とチェーン店の活用も紹介【GMOおみせアプリ成功事例12選】
今回は、飲食店を経営する上で直面しやすい問題やその解決法、そしてこれから開業される人向けの開業ステップについて簡単にご説明しました。
失敗例から学べるたくさんのヒントを元に、自店舗の経営の参考としていただければと思います。
【参考・参照】

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。