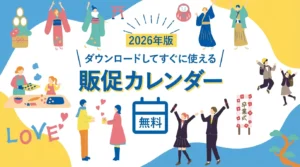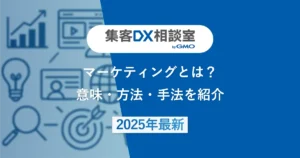2026年の販促カレンダー【無料プレゼント】

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。


2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。
消費者の購買行動モデルは自社商品の販売戦略にとって重要です。
店舗経営者やビジネスオーナーにとって一番の課題は、自社の商品をいかに多く販売し利益を得るかです。
しかしいくら自社の商品が消費者にとって良いものであっても、マーケティングの戦略が間違っていれば、消費者の手元に届くことはないでしょう。
この記事で紹介する購買行動モデルをもとに戦略を立案することで、効果的に自社商品の販売を進めることができます。
購買行動モデルとは、企業が販売する商品やサービスを消費者が認知し、最終的に購入に至るまでのプロセスを図式化したものです。
消費者の購買プロセスには様々な行動や心理が絡み合っており、それらを十分に把握したうえで戦略を立てることが成功の鍵となります。
インターネットやSNSが普及した現在、ただ闇雲に商品のメリットを強調するだけでは、思ったように商品は売れません。なぜなら消費者の購買行動モデルは、時代やインフラの普及などとともに変化し続けているからです。
これから詳しく解説する消費者の購買行動モデルを知り、これらをもとに戦略を立てることができれば、成果に繋がる道筋がみえてくるかもしれません。
はじめにこれまで「古典」として使われてきた購買行動モデルを2つ紹介します。
その誕生は100年ほど前までさかのぼり、現在の購買行動モデルの基礎となっているモデルです。とはいえ今でも使われているケースがあるので、覚えておいて損はありません。
その2つの購買行動モデルが、AIDAとAIDMAです。
AIDAとは消費者の商品購入までのプロセスを示した最初のモデルとして有名です。
順番に
の頭文字を並べたもので、消費者の購入に至るまでの行動や心理を表しています。
インターネットが普及する前、商品をアピールする方法は新聞や雑誌、折り込みチラシ、テレビCMなどが中心でした。それらを見た消費者は商品に注目し(Attention)、興味(Interest)を持ち、欲しい(Desire)という感情を抱き、購入するという行動(Action)を取ります。
そのため企業は「いかに商品に注目し興味を持ってもらえるか」を重要視し、魅力的なキャッチコピーや目をひく画像などを広告に掲載したのです。
いくら商品に対する欲求がわく段階に辿り着いても、すぐに購入に至るとは限りません。人間というのはすぐに忘れてしまう生き物だからです。
そこで生まれたのがAIDMAという購買行動モデルです。DesireのあとにMemory(記憶)が追加されました。せっかく消費者の欲求を刺激したのに、忘れ去られてしまっては意味がありません。
そのため企業は、自社の商品を消費者の記憶(Memory)に留めておいてもらうため、何度もCMを流したりDMを送ったりするわけです。ちなみに現代のメールマガジン(メルマガ)も、この役割を果たしています。
【活用事例】
インターネットやSNSが普及した現在、消費者は日々多くの広告を目にしています。つまり広告を「見飽きている」状態といえます。
一生懸命アピールしても「どうせ広告でしょ」と見破られ、肝心の中身を見てもらえなければ意味がありません。今の時代にマッチした購買行動モデルを活用することが必要です。
AISASとは、インターネットの普及によって誕生した購買行動モデルです。
順番に
の頭文字を表しています。
AISASはAIDAやAIDMAに似ていますが、Desire(欲求)がSearch(検索)に置き換わり、最後にShare(共有)が追加されているところがインターネット時代らしいモデルです。
インターネットの普及により、消費者が興味のわいた商品をすぐに買うことは稀です。なぜなら「買って失敗したくない」という心理が働くからです。
欲しい商品があればGoogleやYahoo!などで検索(Search)し、口コミなどの情報を仕入れてから行動を起こします。そして購入した商品は、口コミやSNSに投稿して共有(Share)。
インターネットショッピングで買い物をする消費者が多くなった時代を象徴するような購買行動モデルです。
AISCEASは、先ほどのAISASを更に詳細化したものです。
順番に
の頭文字を表しており、Comparison(比較)とExamination(検討)が追加されているのがポイントになっています。
AISASと同様、購入前には比較サイトや個人ブログなどで商品を比較したり検討したりすることにより、購入へとつなげます。
ここまでの購買行動モデルは、企業が仕掛ける広告などに対する消費者の注目(Attention)が起点となっていました。しかし先述のとおり、消費者の広告に対する警戒心はますます強くなっています。そこで最近主流になってきているのが「コンテンツマーケティング」です。
コンテンツマーケティングとは、企業がユーザーに役立つ情報をブログなどで紹介し、消費者との信頼関係を高めた上で自社の商品やサービスの購入につなげようとする手法です。ここで紹介するDECAXは、このコンテンツマーケティングにマッチした購買行動モデルになっています。
DECAXは順番に
を表しています。
ある悩みを抱えた消費者が自分に役立ちそうなコンテンツを発見(Discovery)し、「このコンテンツはとても役に立つ」と徐々に関係を構築(Engagement)。
その後企業が販売している商品やサービスが「本当に自分にとって必要か」を確認(Check)し、購入などの行動(Action)を取ります。そしてその商品を体験(eXperience)したあと、SNSなどで共有します。
コンテンツマーケティングにおいて重要なのは、商品を直接的にアピールすることではなく、ユーザーにとって役に立つコンテンツを提供し続けることによって、消費者との関係構築を優先するという点です。
ULSSASはツイッターやインスタグラムなど、SNSの影響を色濃く表す購買行動モデルと言えます。
順番に
の頭文字です。
UGCとは企業から発信されるコンテンツではなく、人(ユーザー)の手によって作られたコンテンツを表します。SNSでは誰かが発信した投稿に対して「いいね」が付けられたりリツイートされたりして、瞬く間に情報が拡散します。このようにユーザーの手によって届けられるコンテンツがUGCです。
SNSが日常となった現代において、UGCは人の購買行動に大きな影響を与えます。「フォロワーさんがおすすめしていた」「リツイートされていたのを見て気になった」などがきっかけとなり、消費者は検索(Search)を始め、行動(Action)を起こし、SNS上で拡散(Spread)します。
ULSSASの大きな特徴は、拡散され続ける限り購買行動パターンが回り続けることです。誰かが商品を購入しSNSで投稿が拡散されれば、それを見た別の消費者がその商品を購入し、再び拡散されることになります。
【活用事例】
購買行動モデルではインターネットやSNSの普及によって、その形式を変化させてきました。特に一番の変化はユーザー体験が口コミなどによって他人に共有される点であるといえます。
マーケティング活動においても共有されることに念頭を置いて戦略を立てる必要があります。各種媒体を効果的に利用し、自社サービスが好意的に受け止められるように対策を講じていくべきでしょう。
当サイトではSNSを利用したマーケティング手法や事例を紹介しています。購買行動モデルに沿った戦略を練るのに参考にしていただけたら幸いです。
【活用事例】

2026年にますます飛躍を遂げていただけるよう販促カレンダーを準備しました。
このカレンダーを販促計画にお役立ていただけたら幸いです。